2025年10月に読んだ本
2025/10/30 Thu Filed in: 読んだ本
・トマトスープ著「天幕のジャードゥーガル 1〜5」(秋田書店ボニータコミックス)
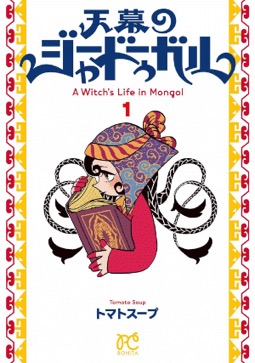
いままで読みたいと思っていて買うことを躊躇していた漫画。舞台は13世紀のモンゴル帝国。主人公はイラン東部の町トゥースの女奴隷、シタラ。学者一家の聡明な奴隷だったシタラはモンゴル帝国の膨張に巻き込まれ、流れ流れてモンゴル帝国のオゴデイの妃、ドレゲネの侍女となる。シタラ(もとの女主人の名ファーティマと改名)はモンゴル帝国への復讐心からその地位を利用して妃を通じて政治工作を繰り広げる。モンゴル帝国の後宮の女性たちも、それぞれの思惑からモンゴル帝国のリーダー(大ハーンや将軍たち)への謀略を進めていき、そこで自由に動けるシタラを利用しようとする。
ざっと言えばそんな話である。モンゴル帝国と言えばチンギス・ハーンかフビライにしか関心は向かないが、オゴデイやチャガタイ、グユク、トゥルイなどに注目しているのはユニークである。トマトスープは漫画家としてのペンネームだが、女性らしい。手塚治虫に少し似た筆致で歴史漫画を描いている。人物の見分けが難しい、近接したキャラクターがちょっと難点。
当時の女性だけでそこまで深い陰謀が描けたのかどうかは疑問だが、これからの展開がどうなるのか、興味は湧く。
この漫画もアニメ化が予定されているらしい。
・幸村 誠著「ヴィンランド・サガ 29」(講談社アフタヌーンコミックス)
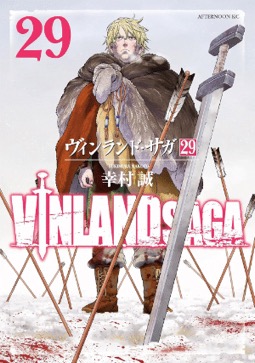
ついに29巻で完結。11世紀に実在した商人トルフィン・ソルザルソンをモデルとする物語も、ヴィンランドでの植民活動のさなか、先住民との対立や先住民に流行しはじめた疫病をめぐって窮地に立たされる。
村のリーダー、トルフィンはあくまでも平和的に先住民との友好を重視し、植民村からの一時撤退も決意するのだが、すでにこの地で苦労を重ねながら生活を軌道に乗せてきた村民にとっては、撤退は考えられない。対立する先住民からの攻撃を受けると自己防衛のために先住民を殺戮し、平和的だった村民も攻撃的に傾斜していく。
少年時代に短剣一本で激しく戦ってきたトルフィンには、すでに力による決着を超越した決意が確固たるものとなっていた。彼だけがあくまでも村の存亡の危機に流されず、先住民との共存を実現しようとしている。今まで共に歩んできた親友ですらも、先住民に対する憎悪にまみれ、ついに命を落とす。
誰が本当の戦士なのか?
真の戦士とは、父の最期を見届けたトルフィンの中でのみ完成していた・・・
この漫画も、すでにアニメ化が何度かに分けて行われている。
・森山 伸也編「FREE HEEL BOOK -Telemark Ski- vol.2」(同人誌)
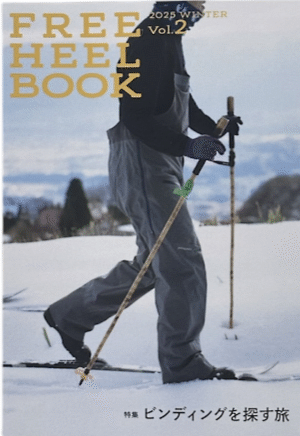
新しいスキー板に今までの古い板からビンディングを移植するための付け替え作業のため、目白のカラファテに立ち寄った際に見つけて衝動買いした本。価格は3,300円だが、こういう本を購入するのに価格の高さを云々言ってはいけない。私自身、テレマークビンディングを探す長い旅の途中である。
テレマークスキーをいまコンスタントに滑っている人口はどのくらいなのだろうか?
私がテレマークスキーを始めた1990年代前半の頃に比べると、特定のスキー場や雪山に集中するのではなく、全国に分散したような気がする。一方、当時初心者として技術の向上に明け暮れていたために、かつての方がずっと熱気があったような気もしている。
この本を読むと、ビンディングにこだわる人たちの細かなセッティングや部品選びが詳細に書かれていて熱気が伝わってくる。アルペンスキーのビンディングとは異なり、テレマークスキーのビンディングはスキーヤーの骨格や体格、滑りのクセ、どんなブーツを履いているか、になどによって千差万別であっておかしくない。それだけ、テレマークのあり方は正解が広い。そのために、軽量・シンプル、自分に合ったビンディングをフランケンシュタインのように別々の製品の組み合わせから作ってしまう人もいるのだ。もちろん、規格が明確に定まっているわけではないから、部品の寄せ集めだけでは使い物にならず、手製のパーツを組み合わせて納得のいくものに仕上げている。その努力は見上げたものだ。私にはそこまで拘れるだけの動機がない。
この本の入手先はこちらから
・藤田 直哉著「攻殻機動隊論 新版2025」(作品社)
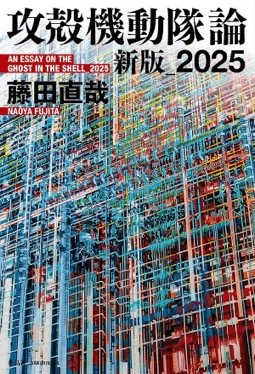
10月半ばからは3冊の本を平行して呼んでいたので、どの本もなかなか読了までに至らなかった。この『攻殻機動隊論』と、野家啓一『パラダイムとは何か クーンの科学史革命』、松原圭一郎『海を越えて 人の移動をめぐる物語』である。『攻殻機動隊論』だけは月末にようやく読み終えた。しかし、この本(紙で買っている)の総ページは380ページ。ポイントも小さくてなかなか読了するのには骨が折れた。
「攻殻機動隊」は1989年に連載が始まった士郎正宗の漫画を発端として、95年の押井守監督『攻殻機動隊 ghost in the shell」を起点とするアニメ映画、TVシリーズなどを指す。最近ではNetflixで配信された『攻殻機動隊 2045』の2つのシリーズがある。また26年には新しい「攻殻機動隊」のアニメ版が予定されている。
これらの映像作品についてそれぞれ論じているのがこの本である。時に南海でわかりにくく、よくある評論本の形式だが、映像は何度も見ているのでそれなりに楽しめた。
今月は3冊を平行して呼んでいたこともあるが、なかなか読書時間を確保できなかった・・
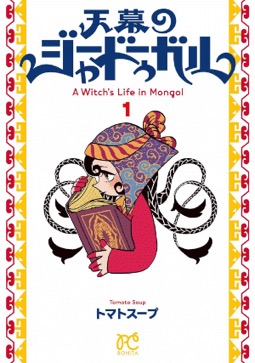
いままで読みたいと思っていて買うことを躊躇していた漫画。舞台は13世紀のモンゴル帝国。主人公はイラン東部の町トゥースの女奴隷、シタラ。学者一家の聡明な奴隷だったシタラはモンゴル帝国の膨張に巻き込まれ、流れ流れてモンゴル帝国のオゴデイの妃、ドレゲネの侍女となる。シタラ(もとの女主人の名ファーティマと改名)はモンゴル帝国への復讐心からその地位を利用して妃を通じて政治工作を繰り広げる。モンゴル帝国の後宮の女性たちも、それぞれの思惑からモンゴル帝国のリーダー(大ハーンや将軍たち)への謀略を進めていき、そこで自由に動けるシタラを利用しようとする。
ざっと言えばそんな話である。モンゴル帝国と言えばチンギス・ハーンかフビライにしか関心は向かないが、オゴデイやチャガタイ、グユク、トゥルイなどに注目しているのはユニークである。トマトスープは漫画家としてのペンネームだが、女性らしい。手塚治虫に少し似た筆致で歴史漫画を描いている。人物の見分けが難しい、近接したキャラクターがちょっと難点。
当時の女性だけでそこまで深い陰謀が描けたのかどうかは疑問だが、これからの展開がどうなるのか、興味は湧く。
この漫画もアニメ化が予定されているらしい。
・幸村 誠著「ヴィンランド・サガ 29」(講談社アフタヌーンコミックス)
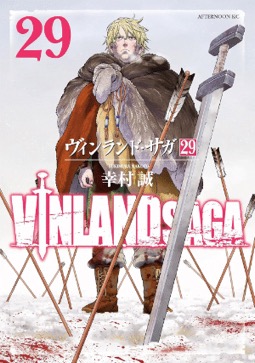
ついに29巻で完結。11世紀に実在した商人トルフィン・ソルザルソンをモデルとする物語も、ヴィンランドでの植民活動のさなか、先住民との対立や先住民に流行しはじめた疫病をめぐって窮地に立たされる。
村のリーダー、トルフィンはあくまでも平和的に先住民との友好を重視し、植民村からの一時撤退も決意するのだが、すでにこの地で苦労を重ねながら生活を軌道に乗せてきた村民にとっては、撤退は考えられない。対立する先住民からの攻撃を受けると自己防衛のために先住民を殺戮し、平和的だった村民も攻撃的に傾斜していく。
少年時代に短剣一本で激しく戦ってきたトルフィンには、すでに力による決着を超越した決意が確固たるものとなっていた。彼だけがあくまでも村の存亡の危機に流されず、先住民との共存を実現しようとしている。今まで共に歩んできた親友ですらも、先住民に対する憎悪にまみれ、ついに命を落とす。
誰が本当の戦士なのか?
真の戦士とは、父の最期を見届けたトルフィンの中でのみ完成していた・・・
この漫画も、すでにアニメ化が何度かに分けて行われている。
・森山 伸也編「FREE HEEL BOOK -Telemark Ski- vol.2」(同人誌)
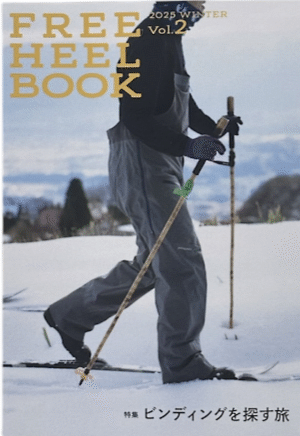
新しいスキー板に今までの古い板からビンディングを移植するための付け替え作業のため、目白のカラファテに立ち寄った際に見つけて衝動買いした本。価格は3,300円だが、こういう本を購入するのに価格の高さを云々言ってはいけない。私自身、テレマークビンディングを探す長い旅の途中である。
テレマークスキーをいまコンスタントに滑っている人口はどのくらいなのだろうか?
私がテレマークスキーを始めた1990年代前半の頃に比べると、特定のスキー場や雪山に集中するのではなく、全国に分散したような気がする。一方、当時初心者として技術の向上に明け暮れていたために、かつての方がずっと熱気があったような気もしている。
この本を読むと、ビンディングにこだわる人たちの細かなセッティングや部品選びが詳細に書かれていて熱気が伝わってくる。アルペンスキーのビンディングとは異なり、テレマークスキーのビンディングはスキーヤーの骨格や体格、滑りのクセ、どんなブーツを履いているか、になどによって千差万別であっておかしくない。それだけ、テレマークのあり方は正解が広い。そのために、軽量・シンプル、自分に合ったビンディングをフランケンシュタインのように別々の製品の組み合わせから作ってしまう人もいるのだ。もちろん、規格が明確に定まっているわけではないから、部品の寄せ集めだけでは使い物にならず、手製のパーツを組み合わせて納得のいくものに仕上げている。その努力は見上げたものだ。私にはそこまで拘れるだけの動機がない。
この本の入手先はこちらから
・藤田 直哉著「攻殻機動隊論 新版2025」(作品社)
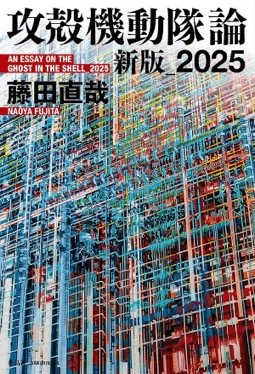
10月半ばからは3冊の本を平行して呼んでいたので、どの本もなかなか読了までに至らなかった。この『攻殻機動隊論』と、野家啓一『パラダイムとは何か クーンの科学史革命』、松原圭一郎『海を越えて 人の移動をめぐる物語』である。『攻殻機動隊論』だけは月末にようやく読み終えた。しかし、この本(紙で買っている)の総ページは380ページ。ポイントも小さくてなかなか読了するのには骨が折れた。
「攻殻機動隊」は1989年に連載が始まった士郎正宗の漫画を発端として、95年の押井守監督『攻殻機動隊 ghost in the shell」を起点とするアニメ映画、TVシリーズなどを指す。最近ではNetflixで配信された『攻殻機動隊 2045』の2つのシリーズがある。また26年には新しい「攻殻機動隊」のアニメ版が予定されている。
これらの映像作品についてそれぞれ論じているのがこの本である。時に南海でわかりにくく、よくある評論本の形式だが、映像は何度も見ているのでそれなりに楽しめた。
今月は3冊を平行して呼んでいたこともあるが、なかなか読書時間を確保できなかった・・
2025年9月に読んだ本
2025/09/08 Mon Filed in: 読んだ本
・安田 浩一著「地震と虐殺 1923ー2024」(中央公論新社)
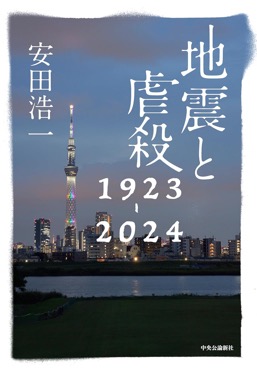
昨年秋に購入して、「積ん読」状態のまま1年が経ちそうだった。8月後半から読み始め、9月上旬に読了した。関東大震災から100年の年に読むよりも、関東大震災の起こったのと同じ時期に読みたかった。紙の書籍だと600ページもある大著である。
関東大震災直後、東京をはじめ、千葉、神奈川、群馬などで朝鮮人労働者や中国人労働者がかなりの数殺害された。これは否定することはできない事実である。この事実から目を背けたり、まして虐殺事件はなかったなどという世迷言を主張する者が現れ始め、各地の自称「保守」(実は保守の本質から大きく外れている)政治家たちがそれに便乗している。東京都知事小池百合子しかり、群馬県議会しかり。歴史を直視できない政治家は退場願いたい。
著者は各地の虐殺事件を追って現場を何度も訪れている。私の自宅がある近辺では震災直後にいくつもの虐殺事件が起こっているが、それらを文字で追うだけで痛ましい。昨年公開された映画、「福田村事件」も千葉県野田市での虐殺事件、しかも朝鮮出身者と見間違えられた香川県からの行商人が複数人、自警団の者たちに虐殺された。このような民衆たちによる虐殺事件は民衆の視野の狭さ、根拠のない噂に便乗してしまう弱さを著しているが、その背後で虐殺をけしかけ、自らも虐殺を率先して行った警察・軍隊の影響が強い。
著者のおかげで、虐殺を描いた絵画から、福島県西郷村でも虐殺事件が起こっていたことを知った。
・横山 百合子著「江戸東京の明治維新」(岩波新書)
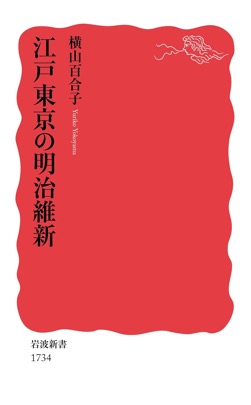
江戸末期から明治維新直後までの江戸の社会史を扱った本。大名屋敷の衰退と旧幕臣の生活、町人の暮らしっぷりや遊廓の変化、屠殺場の民衆など、一風変わったスポットを取り上げて論述している。
本書の「おわりに」に記された一節がこの本の特徴をよくあらわしているので、それを引用してみる。
「江戸東京の人びとにとって、明治維新とは何だったのか。混沌とする時代のなかで、旧来の身分の論理に拠って粘り強くたたかった者もあれば、集団から独立し、近代の一自営業者として新規事業に果敢に挑戦していく者もいた。役にたいする特権集団から、権利としての営業の自由と団結に気づきはじめる商人たちの姿もあった。維新を生きるとは、そうしたそれぞれの可能性を模索することであった。」
特に新吉原の遊女、「かしく」が社会的弱者であるにも関わらず精いっぱい自分の解放を求めて動く様は、感動的でもある。
・大山 顕著「マンションポエム東京論」(本の雑誌社)
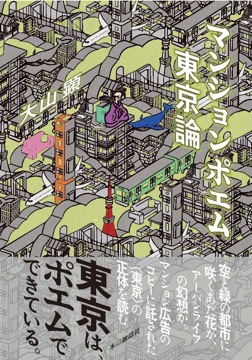
筆者はかつてテレビ番組「熱中時間 忙中"趣味"あり」にレギュラーとして出演していたコラムニストで、団地・工場・ジャンクションマニアとして知られていた人物である。この番組はけっこう好きで観ていたが、団地好きが高じてマンション広告の「ポエム」について掘り下げ、この本を上梓するに至ったことは、さして驚くできごとではなかった。
なかなか充実した書物である。今回は電子書籍が見つからなかったので、紙の本をネットで注文してお茶の水の丸善まで取りに行った。2段組、約350ページ。ある種学術的な本ではあるが、対象がマンションなので内容は分かりやすい。
「マンションポエム」とは、マンションの広告に掲載されているキャッチコピーである。たとえば、先の東京オリンピックの選手村を活用した「晴海フラッグ」は「美しい景色を眺めるたびに、町への愛着は深まっていくはずです。」銀座に近い高級マンションは「羨望の都心立地。」ここ数年で開発されタワーマンションが林窒する有明地区のマンションは「世界の羨望を集める 新たな中心を日本に。」といった具合である。
口の中に食べ物が入っていると外に飛び出しそうな噴飯物のコピーだが、筆者はもう25年もこういったコピーを集め、研究対象にしてきた。ポエムの対象は東京だけでなく、首都圏から関西(大坂・京都)地方都市にまで及ぶ。それらを読んでいるだけで面白いが、決してふざけた本ではない。マンションの構造や利便性は、東京だろうが地方都市だろうが、同年代に建設されたものであればさほど変わらない。問題は立地である。都心部からどのくらいの距離にあるのか、駅から徒歩何分なのか、公園や学校は近いのか、といった情報がその立地の価値を過剰に高め(あるいは高めることが困難で)マンションポエムに結びつくのだ。そういう点で、生々しい負の情報をマンションポエムは秘匿する役割を持つという。けだし名言だと思う。
・武田 砂鉄著「いきりの構造」(朝日新聞出)
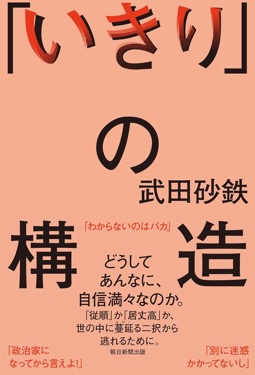
武田砂鉄の最新刊。彼の著作はかなり読んできた。「紋切型社会」以降、取り上げる問題や、ねちっこくて時に主旨が汲み取りにくい文体がほとんど変わっていないのがいい。
「いきり」とは何なのか?
暴走したりルールやマナーを守らない走行を繰り返す車両を見て、「イキった運転だなあ」と感想を漏らすことが自分にはある。例えば通勤中に見かけるのは、車線を踏んだまま右に行くのか左に車線変更するのかわかりにくい運転、事前にウィンカーを出さず、交差点の直前で急に点滅させ、右にいったん寄せてから左折する軽自動車、もちろん、「煽り運転」に限りになく近い、車間距離をとらない運転・・実は運転が「下手」だということをこれらの行為で表面化してしまっている。
日常生活上で「イキる」人を眼前で見かけたことはあまりないが、一言で言えば「自己中」な人、その強がった発言。他人からの異論に対して、自分の「正義」がまったく揺るがない態度を見せる人(相手の反論を「切り取り」と吐き捨てるような行為)、反吐が出るような自己防衛。武田砂鉄も、「おわりに」で「『いきり』は防衛なのだ」と述べている。
「いきり」は見苦しい。
・トマトスープ著「天幕のジャードゥーガル」(秋田書店 ボニータ・コミックス)
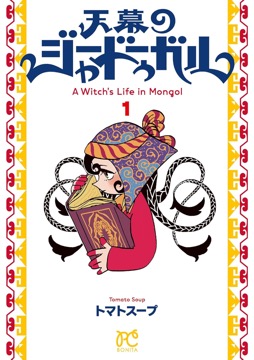
新しい漫画シリーズを手に入れて(実は大人買いして)読み始めた。まだ第1巻のみにとどめている。
13世紀初頭のモンゴル帝国の勢力拡大によって制圧されつつあった、イラン北東部(現在ならトゥルクメニスタン国境近く)の都市トゥースに住まう学者家族の少女奴隷、ステラ(のちにファーティマ)に起こる数奇な運命を描いている。
イランはイスラーム圏にあり、イスラーム圏での奴隷の扱い(19世紀のアメリカのそれとは大きく異なる)や学術を重んじる文化がよく描かれている。対するモンゴルは、自らを文化的には劣っていて、高度な学問を受け入れる意欲を持った社会と認めている。モンゴルによる中央アジア征服の中で、降伏と恭順の勧告を受け入れず、あくまでもモンゴルに抵抗する意志を持った都市では殺戮が行われたことが描かれている(これは事実である)。
フィクションではあるが、史実を踏まえて創られた物語であることは評価できそうだ。最近はそういった学術的な支えの中で描かれる漫画が増えて嬉しい。ただし、漫画の絵柄は、好みが分かれるところかもしれない。
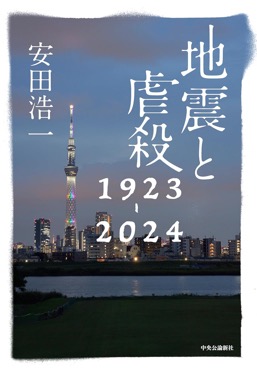
昨年秋に購入して、「積ん読」状態のまま1年が経ちそうだった。8月後半から読み始め、9月上旬に読了した。関東大震災から100年の年に読むよりも、関東大震災の起こったのと同じ時期に読みたかった。紙の書籍だと600ページもある大著である。
関東大震災直後、東京をはじめ、千葉、神奈川、群馬などで朝鮮人労働者や中国人労働者がかなりの数殺害された。これは否定することはできない事実である。この事実から目を背けたり、まして虐殺事件はなかったなどという世迷言を主張する者が現れ始め、各地の自称「保守」(実は保守の本質から大きく外れている)政治家たちがそれに便乗している。東京都知事小池百合子しかり、群馬県議会しかり。歴史を直視できない政治家は退場願いたい。
著者は各地の虐殺事件を追って現場を何度も訪れている。私の自宅がある近辺では震災直後にいくつもの虐殺事件が起こっているが、それらを文字で追うだけで痛ましい。昨年公開された映画、「福田村事件」も千葉県野田市での虐殺事件、しかも朝鮮出身者と見間違えられた香川県からの行商人が複数人、自警団の者たちに虐殺された。このような民衆たちによる虐殺事件は民衆の視野の狭さ、根拠のない噂に便乗してしまう弱さを著しているが、その背後で虐殺をけしかけ、自らも虐殺を率先して行った警察・軍隊の影響が強い。
著者のおかげで、虐殺を描いた絵画から、福島県西郷村でも虐殺事件が起こっていたことを知った。
・横山 百合子著「江戸東京の明治維新」(岩波新書)
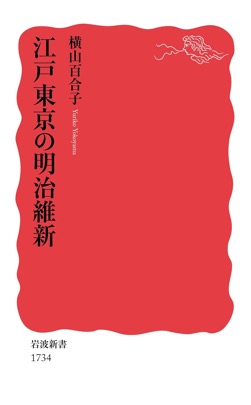
江戸末期から明治維新直後までの江戸の社会史を扱った本。大名屋敷の衰退と旧幕臣の生活、町人の暮らしっぷりや遊廓の変化、屠殺場の民衆など、一風変わったスポットを取り上げて論述している。
本書の「おわりに」に記された一節がこの本の特徴をよくあらわしているので、それを引用してみる。
「江戸東京の人びとにとって、明治維新とは何だったのか。混沌とする時代のなかで、旧来の身分の論理に拠って粘り強くたたかった者もあれば、集団から独立し、近代の一自営業者として新規事業に果敢に挑戦していく者もいた。役にたいする特権集団から、権利としての営業の自由と団結に気づきはじめる商人たちの姿もあった。維新を生きるとは、そうしたそれぞれの可能性を模索することであった。」
特に新吉原の遊女、「かしく」が社会的弱者であるにも関わらず精いっぱい自分の解放を求めて動く様は、感動的でもある。
・大山 顕著「マンションポエム東京論」(本の雑誌社)
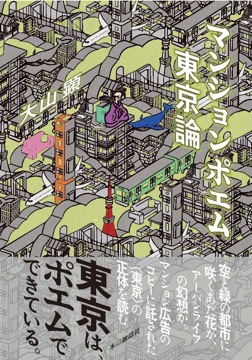
筆者はかつてテレビ番組「熱中時間 忙中"趣味"あり」にレギュラーとして出演していたコラムニストで、団地・工場・ジャンクションマニアとして知られていた人物である。この番組はけっこう好きで観ていたが、団地好きが高じてマンション広告の「ポエム」について掘り下げ、この本を上梓するに至ったことは、さして驚くできごとではなかった。
なかなか充実した書物である。今回は電子書籍が見つからなかったので、紙の本をネットで注文してお茶の水の丸善まで取りに行った。2段組、約350ページ。ある種学術的な本ではあるが、対象がマンションなので内容は分かりやすい。
「マンションポエム」とは、マンションの広告に掲載されているキャッチコピーである。たとえば、先の東京オリンピックの選手村を活用した「晴海フラッグ」は「美しい景色を眺めるたびに、町への愛着は深まっていくはずです。」銀座に近い高級マンションは「羨望の都心立地。」ここ数年で開発されタワーマンションが林窒する有明地区のマンションは「世界の羨望を集める 新たな中心を日本に。」といった具合である。
口の中に食べ物が入っていると外に飛び出しそうな噴飯物のコピーだが、筆者はもう25年もこういったコピーを集め、研究対象にしてきた。ポエムの対象は東京だけでなく、首都圏から関西(大坂・京都)地方都市にまで及ぶ。それらを読んでいるだけで面白いが、決してふざけた本ではない。マンションの構造や利便性は、東京だろうが地方都市だろうが、同年代に建設されたものであればさほど変わらない。問題は立地である。都心部からどのくらいの距離にあるのか、駅から徒歩何分なのか、公園や学校は近いのか、といった情報がその立地の価値を過剰に高め(あるいは高めることが困難で)マンションポエムに結びつくのだ。そういう点で、生々しい負の情報をマンションポエムは秘匿する役割を持つという。けだし名言だと思う。
・武田 砂鉄著「いきりの構造」(朝日新聞出)
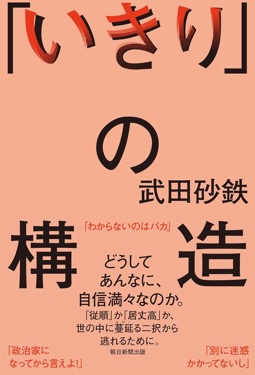
武田砂鉄の最新刊。彼の著作はかなり読んできた。「紋切型社会」以降、取り上げる問題や、ねちっこくて時に主旨が汲み取りにくい文体がほとんど変わっていないのがいい。
「いきり」とは何なのか?
暴走したりルールやマナーを守らない走行を繰り返す車両を見て、「イキった運転だなあ」と感想を漏らすことが自分にはある。例えば通勤中に見かけるのは、車線を踏んだまま右に行くのか左に車線変更するのかわかりにくい運転、事前にウィンカーを出さず、交差点の直前で急に点滅させ、右にいったん寄せてから左折する軽自動車、もちろん、「煽り運転」に限りになく近い、車間距離をとらない運転・・実は運転が「下手」だということをこれらの行為で表面化してしまっている。
日常生活上で「イキる」人を眼前で見かけたことはあまりないが、一言で言えば「自己中」な人、その強がった発言。他人からの異論に対して、自分の「正義」がまったく揺るがない態度を見せる人(相手の反論を「切り取り」と吐き捨てるような行為)、反吐が出るような自己防衛。武田砂鉄も、「おわりに」で「『いきり』は防衛なのだ」と述べている。
「いきり」は見苦しい。
・トマトスープ著「天幕のジャードゥーガル」(秋田書店 ボニータ・コミックス)
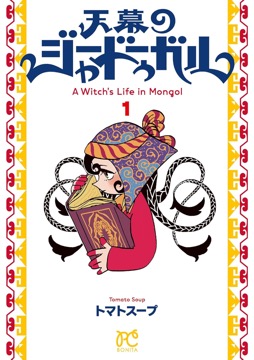
新しい漫画シリーズを手に入れて(実は大人買いして)読み始めた。まだ第1巻のみにとどめている。
13世紀初頭のモンゴル帝国の勢力拡大によって制圧されつつあった、イラン北東部(現在ならトゥルクメニスタン国境近く)の都市トゥースに住まう学者家族の少女奴隷、ステラ(のちにファーティマ)に起こる数奇な運命を描いている。
イランはイスラーム圏にあり、イスラーム圏での奴隷の扱い(19世紀のアメリカのそれとは大きく異なる)や学術を重んじる文化がよく描かれている。対するモンゴルは、自らを文化的には劣っていて、高度な学問を受け入れる意欲を持った社会と認めている。モンゴルによる中央アジア征服の中で、降伏と恭順の勧告を受け入れず、あくまでもモンゴルに抵抗する意志を持った都市では殺戮が行われたことが描かれている(これは事実である)。
フィクションではあるが、史実を踏まえて創られた物語であることは評価できそうだ。最近はそういった学術的な支えの中で描かれる漫画が増えて嬉しい。ただし、漫画の絵柄は、好みが分かれるところかもしれない。
2025年8月に読んだ本
2025/08/12 Tue Filed in: 読んだ本
・吉田 修一著「国宝 下」(朝日新聞出版)
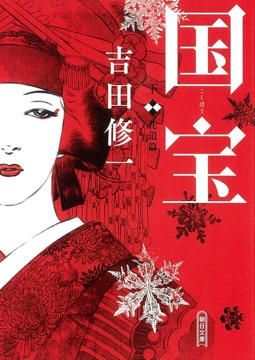
7月に読んだ上巻に続いて、下巻も読み終えた。映画も面白かったが、原作はさらに深みが増していて、映画をさらに複雑にした「深み」があった。実はこの小説の主人公は役者の喜久雄ではなく、喜久雄の影のようにふるまい、いつの間にか喜久雄の前から姿を消していた徳次(映画冒頭で座敷芸を喜久雄と演じていた、当時の喜久雄の兄貴分)ではないか、という気持ちにさせる。映画のほとんどはこの小説に忠実に、あるいは順序をずらして引用されたものだが、徳次や喜久雄の父親の死因については最後の最後まで伏線回収が成されないところが面白く、突然場面転換があってそこで書かれている内容を理解すると、急に腑に落ちるという構造になっている。
解説にある実際の歌舞伎の演目とこの小説との深い関連については、歌舞伎の知識がないだけに理解できず残念である。
・岩間 一弘著「中華料理と日本人 帝国主義から懐かしの味への100年史」(中公新書)
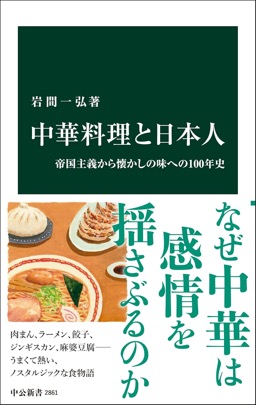
この本で取り上げられる中華料理(街の中華料理店やコンビニでポピュラーなメニュー)としては、肉まん、餃子、ウーロン茶、シュウマイ、ラーメン、麻婆豆腐である。
それぞれ私たちに馴染みの深い庶民的なもので、興味深く読んだが、本文が電子書籍の50%しかないのは残念。実に損した感じがする。
これが紙の本で半分しか本文がなく、のこりが全て注釈や参考文献だったらどうだろう?このような新書では、参考文献はもっと絞り込んで、内容を充実させるか、本一冊の価格を下げるべきだ。
・辻田 真佐憲著「『あの戦争』は何だったのか」(講談社現代新書)
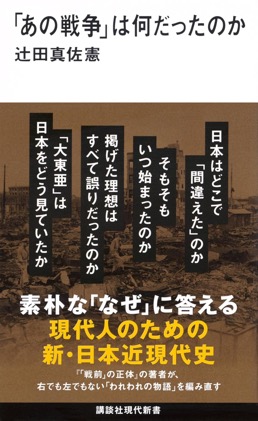
戦後80年の節目に読んでみた。辻田氏の著作は「戦前の正体」(講談社現代新書)を過去に読んでいる。
今回、日本が行ってきた戦争の呼称についての考察があり、興味深く読んだ。「太平洋戦争」「第二次世界大戦」「アジア・太平洋戦争」「十五年戦争」「大東亜戦争」などなど。石原莞爾の歴史観に従って江戸末期の開国が戦争への原点だという節も紹介してくれた。
そこで、辻田氏は「大東亜戦争」が最もふさわしいという個人的見解を持っているという。なかなか思い切った口上だが、誤解を与えかねない。
「大東亜戦争」の呼称は1941年の米英開戦によって戦争の呼称として東條内閣で閣議決定された呼称だが、戦後まもなくGHQから使用を禁じられ、独立以後も政府として使用しない方針は現在まで貫かれている(太平洋戦争も大東亜戦争も正式な法令上の定義はないという前提で)。「大東亜戦争」の呼称は、戦後は他の用語とフラットに扱うことができなかった経緯がある。かわりに歴史学界で用いられているのが「アジア・太平洋戦争」である。この呼称も本当にふさわしいかと言われれば、辻田氏の言うようにどこからも文句がつけられない「防衛的な」呼称と言われても仕方がない。
では辻田氏は敢えて「大東亜戦争」の呼称を積極的に用い広めようとしているのだろうか。そこに留意しながら先に読み進めていくと、最初に自ら「ふさわしい」と強調しておきながら、やや矛盾する記述が見られる。
例えば「大東亜戦争」=「日中戦争(支那事変とは呼んでいない)」+「太平洋戦争」と定義しているが、「1941年12月、大東亜戦争が勃発した」、と自らの定義から外れる当時の閣議決定に基づく戦争名称と開始時期を記述しているのは、時間軸と呼称に対する揺れが見られる一例である。
「大東亜」とは戦前の近衛内閣で登場した「東亜新秩序」「大東亜共栄圏」の構想を踏まえている(簡単に言えば東亜=日満支、大東亜=日満支を含み、東南アジア、や太平洋海域を含む、1941〜45年の戦闘地域全体)。資源欲しさに対外進出を強める口実となった2つの構想は、そもそも明確なビジョンに基づく構想ではない、ということを辻田氏は分析していく。そこは共感し理解できる。だが「『大東亜共栄圏』と言う用語は元来空疎」、と書きながら戦争名としては「大東亜戦争」がふさわしいといった書きっぷりは首をかしげたくなる。空疎な構想を土台とした戦争、という皮肉としてこの用語を用いるのであれば、そう宣言してから書いた方がいい。
また、歴史学と科学に対する見方にも私には疑問がある。「歴史は究極的に科学ではない、科学とはAとBという試薬を一定条件で混ぜれば必ずXという結果が得られるもの」、としているが、科学に対する理解が皮相的で一面的ではないだろうか。上のような主張は感覚的にはわかるものの、科学はそんなに単純なものではないはずだ。1つの結論だけが帰着点で、複数のプロセスが認められないというものでもなかろう。自然科学だって、大きなパラダイム転換を複数回繰り返してきた。歴史全体を揺るがすようなパラダイム転換はなかなか起こり得ないが、具体的な細部の見方についてはしょっちゅう変化し、既存の見方が覆されている。そういう意味では、歴史だって科学なのである。
合理的な分析と推論によって導かれた結論が「科学」を構成していて、その結論も観点の違いや批判によってより合理的で多数が納得できるような結論に置き換えられ得るもの、が科学的な学問だと私は思っている。自分の感情や都合、少数者の論証のない願望によって置き換えられるような結論は歴史的結論とは遠いところにある。
細かなことではあるが、「満州」ではなく「満洲」と正式な地名を書いているのに、東條英機については「東条」と略字を使っているのも気になる。子孫は「東條」を用いているのだから、そちらにあわせるべきであろう。
その他全体の記述については、納得できるものが多い。特に第4章で東條英機が「大東亜」各地を巡ったことにちなんで各地の歴史博物館などを筆者自らが訪れたことは非常に興味深く読むことができた。
・佐々木 俊尚著「歩くを楽しむ 自然を味わう フラット登山」(かんき出版)
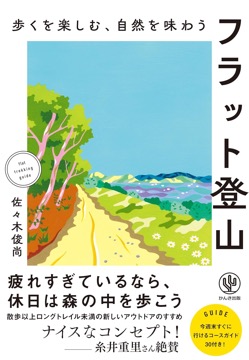
いま、ラジオなどで引っ張りだこの著者・著作である。山頂を目指さない登山をするというのは賛成する。最近はピークハントそのものが目的化しすぎていて、山全体を楽しむということが薄くなっている。百名山ハンターの登山スタイルは好きではないので、いっこうに百名山を完登することがない。自分の生活圏から遠く離れた山は、昔バイクツーリングのついでに登ったことがあるが、何度も行こうとは思わない。長野県の山々だって、県境の山は行ってみたいと思うこともあるが、夏山の混雑ぶりを考えると敬遠したくなる。できれば東北の山のように有人小屋がなく、避難小屋や静かなテント泊で生ける山がいいし、山全体を味わうには山頂だけがすべてではないはずだ。後半は具体的なフラット登山30コースが紹介されていて、四季に応じて歩けるルートが掲載されている。
上記の本のほか、昨年買ってなかなか読み進められなかった、安田浩一著「地震と虐殺 1923ー2024」もちょうど半分読んだが、来月に継続する。
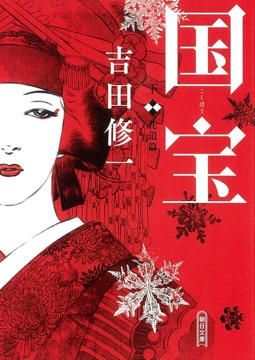
7月に読んだ上巻に続いて、下巻も読み終えた。映画も面白かったが、原作はさらに深みが増していて、映画をさらに複雑にした「深み」があった。実はこの小説の主人公は役者の喜久雄ではなく、喜久雄の影のようにふるまい、いつの間にか喜久雄の前から姿を消していた徳次(映画冒頭で座敷芸を喜久雄と演じていた、当時の喜久雄の兄貴分)ではないか、という気持ちにさせる。映画のほとんどはこの小説に忠実に、あるいは順序をずらして引用されたものだが、徳次や喜久雄の父親の死因については最後の最後まで伏線回収が成されないところが面白く、突然場面転換があってそこで書かれている内容を理解すると、急に腑に落ちるという構造になっている。
解説にある実際の歌舞伎の演目とこの小説との深い関連については、歌舞伎の知識がないだけに理解できず残念である。
・岩間 一弘著「中華料理と日本人 帝国主義から懐かしの味への100年史」(中公新書)
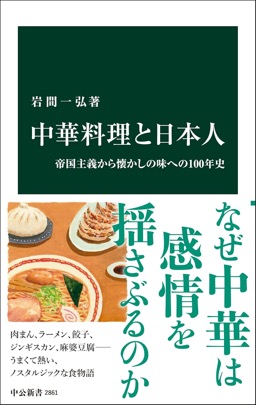
この本で取り上げられる中華料理(街の中華料理店やコンビニでポピュラーなメニュー)としては、肉まん、餃子、ウーロン茶、シュウマイ、ラーメン、麻婆豆腐である。
それぞれ私たちに馴染みの深い庶民的なもので、興味深く読んだが、本文が電子書籍の50%しかないのは残念。実に損した感じがする。
これが紙の本で半分しか本文がなく、のこりが全て注釈や参考文献だったらどうだろう?このような新書では、参考文献はもっと絞り込んで、内容を充実させるか、本一冊の価格を下げるべきだ。
・辻田 真佐憲著「『あの戦争』は何だったのか」(講談社現代新書)
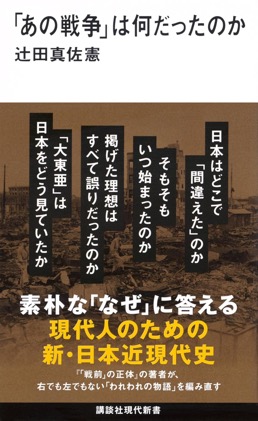
戦後80年の節目に読んでみた。辻田氏の著作は「戦前の正体」(講談社現代新書)を過去に読んでいる。
今回、日本が行ってきた戦争の呼称についての考察があり、興味深く読んだ。「太平洋戦争」「第二次世界大戦」「アジア・太平洋戦争」「十五年戦争」「大東亜戦争」などなど。石原莞爾の歴史観に従って江戸末期の開国が戦争への原点だという節も紹介してくれた。
そこで、辻田氏は「大東亜戦争」が最もふさわしいという個人的見解を持っているという。なかなか思い切った口上だが、誤解を与えかねない。
「大東亜戦争」の呼称は1941年の米英開戦によって戦争の呼称として東條内閣で閣議決定された呼称だが、戦後まもなくGHQから使用を禁じられ、独立以後も政府として使用しない方針は現在まで貫かれている(太平洋戦争も大東亜戦争も正式な法令上の定義はないという前提で)。「大東亜戦争」の呼称は、戦後は他の用語とフラットに扱うことができなかった経緯がある。かわりに歴史学界で用いられているのが「アジア・太平洋戦争」である。この呼称も本当にふさわしいかと言われれば、辻田氏の言うようにどこからも文句がつけられない「防衛的な」呼称と言われても仕方がない。
では辻田氏は敢えて「大東亜戦争」の呼称を積極的に用い広めようとしているのだろうか。そこに留意しながら先に読み進めていくと、最初に自ら「ふさわしい」と強調しておきながら、やや矛盾する記述が見られる。
例えば「大東亜戦争」=「日中戦争(支那事変とは呼んでいない)」+「太平洋戦争」と定義しているが、「1941年12月、大東亜戦争が勃発した」、と自らの定義から外れる当時の閣議決定に基づく戦争名称と開始時期を記述しているのは、時間軸と呼称に対する揺れが見られる一例である。
「大東亜」とは戦前の近衛内閣で登場した「東亜新秩序」「大東亜共栄圏」の構想を踏まえている(簡単に言えば東亜=日満支、大東亜=日満支を含み、東南アジア、や太平洋海域を含む、1941〜45年の戦闘地域全体)。資源欲しさに対外進出を強める口実となった2つの構想は、そもそも明確なビジョンに基づく構想ではない、ということを辻田氏は分析していく。そこは共感し理解できる。だが「『大東亜共栄圏』と言う用語は元来空疎」、と書きながら戦争名としては「大東亜戦争」がふさわしいといった書きっぷりは首をかしげたくなる。空疎な構想を土台とした戦争、という皮肉としてこの用語を用いるのであれば、そう宣言してから書いた方がいい。
また、歴史学と科学に対する見方にも私には疑問がある。「歴史は究極的に科学ではない、科学とはAとBという試薬を一定条件で混ぜれば必ずXという結果が得られるもの」、としているが、科学に対する理解が皮相的で一面的ではないだろうか。上のような主張は感覚的にはわかるものの、科学はそんなに単純なものではないはずだ。1つの結論だけが帰着点で、複数のプロセスが認められないというものでもなかろう。自然科学だって、大きなパラダイム転換を複数回繰り返してきた。歴史全体を揺るがすようなパラダイム転換はなかなか起こり得ないが、具体的な細部の見方についてはしょっちゅう変化し、既存の見方が覆されている。そういう意味では、歴史だって科学なのである。
合理的な分析と推論によって導かれた結論が「科学」を構成していて、その結論も観点の違いや批判によってより合理的で多数が納得できるような結論に置き換えられ得るもの、が科学的な学問だと私は思っている。自分の感情や都合、少数者の論証のない願望によって置き換えられるような結論は歴史的結論とは遠いところにある。
細かなことではあるが、「満州」ではなく「満洲」と正式な地名を書いているのに、東條英機については「東条」と略字を使っているのも気になる。子孫は「東條」を用いているのだから、そちらにあわせるべきであろう。
その他全体の記述については、納得できるものが多い。特に第4章で東條英機が「大東亜」各地を巡ったことにちなんで各地の歴史博物館などを筆者自らが訪れたことは非常に興味深く読むことができた。
・佐々木 俊尚著「歩くを楽しむ 自然を味わう フラット登山」(かんき出版)
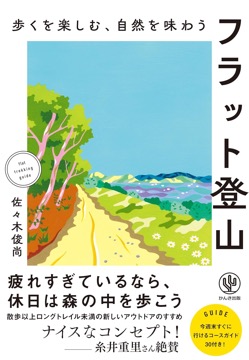
いま、ラジオなどで引っ張りだこの著者・著作である。山頂を目指さない登山をするというのは賛成する。最近はピークハントそのものが目的化しすぎていて、山全体を楽しむということが薄くなっている。百名山ハンターの登山スタイルは好きではないので、いっこうに百名山を完登することがない。自分の生活圏から遠く離れた山は、昔バイクツーリングのついでに登ったことがあるが、何度も行こうとは思わない。長野県の山々だって、県境の山は行ってみたいと思うこともあるが、夏山の混雑ぶりを考えると敬遠したくなる。できれば東北の山のように有人小屋がなく、避難小屋や静かなテント泊で生ける山がいいし、山全体を味わうには山頂だけがすべてではないはずだ。後半は具体的なフラット登山30コースが紹介されていて、四季に応じて歩けるルートが掲載されている。
上記の本のほか、昨年買ってなかなか読み進められなかった、安田浩一著「地震と虐殺 1923ー2024」もちょうど半分読んだが、来月に継続する。
2025年7月に読んだ本
2025/07/29 Tue Filed in: 読んだ本
・相田 豊著「愛と孤独のフォルクローレ ボリビア音楽家と生の人類学」(世界思想社)
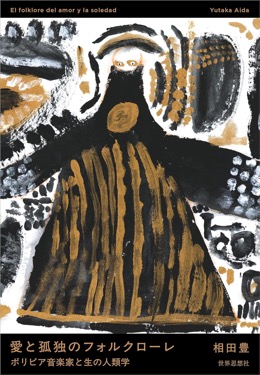
著者の相田さんは、実は私が一時だけ教えたことがあり、その後一時は同僚でもあった。彼は大学で中南米を対象とした人類学を専攻し、同好会でフォルクローレに魅せられ、フォルクローレ研究を進めてサンポーニャの演奏者にもなっているというユニークな研究者であり、現在は上智大学特任助教である。そのような学者がフィールドワークとしてボリビアの音楽家と交流し、文化人類学の論文とは異なるアプローチでこの大部な本を上梓した。博士論文を大幅にリライトしたものだそうだが、硬い論文の文体とは違い、一般読者にも実に読み易く、スルスルと内容がしみ渡ってくる。著者の逡巡も感じながら読んでいける。
・中村 隆之著「ブラック・カルチャー 大西洋を旅する声と音」(岩波新書)
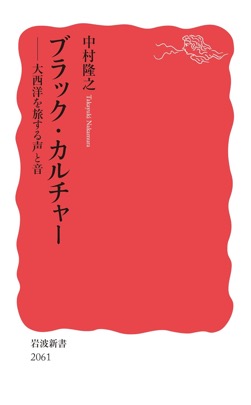
筆者はアメリカ合衆国のブラック・カルチャー専門家というよりは、カリブ海文学の専門家である。大変珍しい専門領域をお持ちのようだが、的確にアメリカ大陸全般のブラック・カルチャーの形成や展開を新書の中でまとめている。特にアメリカ大陸でのアフリカ系民族の奴隷制度との関連で、音楽だけでなく文学なども含めて理解する上では基礎的な内容になっているのだろう。ゴスペル、ジャズ、ソウル、ファンク、ヒップホップなどなど、ブラック・ミュージックを我々はジャンル分けしようとするが、それにはあまり意味はなく、根っこでいずれもが繋がっている。パン・アフリカニズムについて理解が深まったのが収穫だった。
・白井 聡・高瀬 毅(聞き手)「ニッポンの正体2025 世界の二極化と戦争の時代」(河出書房新社)
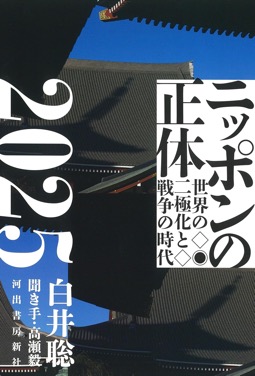
思想史家・政治学者で京都精華大学准教授の白井聡と、ジャーナリスト・ノンフィクション作家の高瀬毅との対談シリーズの最新作。白井の発言はときどき過激なものがあってドキッとする。
話題は国内政治状況(参院選を挟んで読んでいたので大変リアリティがあった)、東京一極集中、「戦後レジーム」について、大学の来し方行く末、労働について、「公助」の崩壊、朝鮮半島有事についてなど、多岐にわたっているが、最後の朝鮮半島有事については韓国の政権交代以前、トランプ再選以前の対談であり、現実が本の中の予測を追い越してしまっているので、賞味期限切れに近い。
全体として非常にわかりやすく、集中すれば数日間で読める。
・吉田 修一著「国宝 上」(朝日新聞出版)
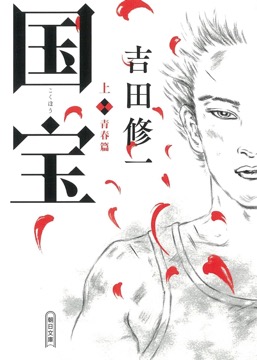
まず映画を鑑賞して、原作を読みたくなり、買い求めた。小説を読むのは実に久しぶりである。映画では描けなかった部分が描かれていて、一気にのめり込んだ。映画では描ききれなかった部分は複数あるのだが、ここで書いてしまっては元も子もないので書かないでおく。映画を観た後に読んでも、原作を先に読んで映画を観に行ってもどちらも楽しめるだろう。文体が「でございます。」というのも非常に珍しく、ユニークであった。上下巻だが、今月中に下巻まで読み切ることは難しかった。
上巻の後半は、主人公喜久雄の役者人生の中での天国と地獄が描かれる。映画では見られなかった、周辺人物や企業からのねちっこいいじめがすさまじい。
・黒田 明伸著「歴史の中の貨幣 銅銭がつないだ東アジア」(岩波新書)
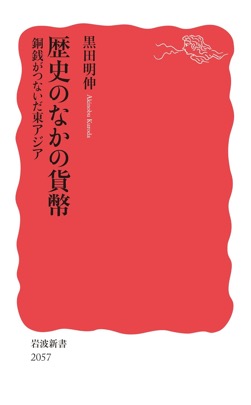
「国宝 上」と平行して月末から読み始めた。これがまたとても面白い内容だった。東アジアの銅銭として最も古いのは秦の半両銭、前漢の五銖銭であり、日本でも和同開珎以後「皇朝十二銭」が発行されてきた、というのが大学受験を前提とした貨幣史の基礎である。
だが、中国でも日本でも、貨幣経済がそのまま右肩上がりに進むのではなく、銅銭の製造に必要な銅鉱石の資源供給や精錬技術のハードルがあり、銅銭の品位の問題や流通範囲の限定などの結果、基本的には高額なもの(土地など)の対価としては絹や麻の布が用いられてきた。日本では、皇朝十二銭以後、戦国時代末期に至るまで自国で鋳造された貨幣は存在せず、中国から流入した銅銭が用いられ、銅銭は鋳つぶされて仏像や梵鐘などに再利用された。
租庸調をはじめ、銭納原則だった両税法でも現実には物納が行われてきた。それが宋代になって精練法の向上によって銅銭が大量発行され、交子や会子という手形から生まれた紙幣すら流通するようになった。このころ、大量に銅銭は日本にもたらされる。
元代になると、紙幣が主要通貨となり、原則中国では銅貨が使用できなくなる。これも大変ユニークなところ。明代初期も同様だが、紙幣のみの貨幣経済が一元的に行われたわけではない。かたや日本では15世紀に精錬技術が飛躍的に向上して銅生産が拡大し、銅は日明貿易(勘合貿易)や倭寇によって中国やヴェトナムに流入する。同じころ、永楽通宝といわれる銅貨が登場するが、日本との貿易にもっぱら使われ、明ではあまり流通せず、しかも私鋳が行われてきた。銅貨を取り巻く状況は非常に複雑で渾沌としていたのである。やがて明末に銀が登場するが、銀はあくまで秤量貨幣であって計数貨幣ではない。一般民衆が手にできるものではなく、末端では銅貨が用いられてきた。
撰銭だとか、貫高制から石高制への転換が室町・戦国時代を通じて日本では行われるが、かつて日本史の授業でならったこれらがいまひとつ腑に落ちないのは、「あとがき」の冒頭で筆者が書いている通りである。多くの人がいまだに完全に理解できていないのではないだろうか?筆者は長年の研究で端的な言葉で説明しているが、この本を読んでも筆者の理解に到達することは難しい。
というように、内容はなかなか難しいのだが、とても興味を引く問題が目白押しだった。特に第6章「貨幣システムと渡来銭」は貨幣制度そのものの理解に新しい視角を与えてくれる。
・石塚 真一著「BLUE GIANT MOMENTUM(5)」(小学館 ビッグコミックススペシャル)
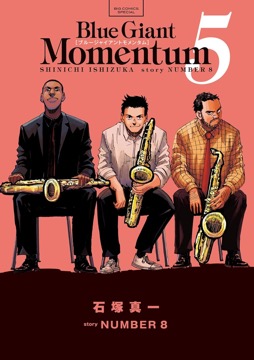
主人公のダイは、バンドメンバーのいるニューヨークを離れ、インターナショナル・ジャズ・コンペティションの行われるミズーリ州セントルイスに単身やってくる。そこで名うての若手サックスプレイヤーと競うべく、定められた10分の演奏を行う。予選を勝ち抜けるのは3人だけ…漫画のストーリーを細かく書くことはしたくないので短いがここまで。
・惣領 冬実著「カンツォニエーレ チェーザレ番外編」(コミックdays 講談社)
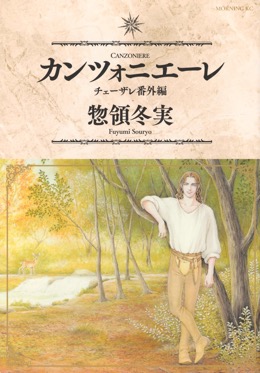
「チェーザレ 破壊の創造者」が13巻でストップしているが、これは本編からのスピンオフ作品。とはいえ、続編のようにも見える。「チェーザレ」第13巻で教皇選挙が行われた後、チェーザレの実父、ロドリーゴが教皇に就任し、チェーザレも枢機卿に任じられる。その時のチェーザレの秘めた恋についてが主題となっている。カンツォニエーレとは、ペトラルカの「抒情詩集」のイタリア語名。
相変わらず絵はきれいだし、惣領冬実が身を削って描いているのが想像できる。
この「チェーザレ」、本編はどうにも終わりそうにないが、スピンオフ作品でその空白を埋めていくのだろうか…
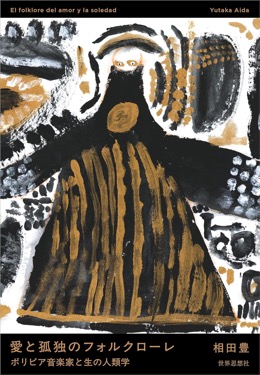
著者の相田さんは、実は私が一時だけ教えたことがあり、その後一時は同僚でもあった。彼は大学で中南米を対象とした人類学を専攻し、同好会でフォルクローレに魅せられ、フォルクローレ研究を進めてサンポーニャの演奏者にもなっているというユニークな研究者であり、現在は上智大学特任助教である。そのような学者がフィールドワークとしてボリビアの音楽家と交流し、文化人類学の論文とは異なるアプローチでこの大部な本を上梓した。博士論文を大幅にリライトしたものだそうだが、硬い論文の文体とは違い、一般読者にも実に読み易く、スルスルと内容がしみ渡ってくる。著者の逡巡も感じながら読んでいける。
・中村 隆之著「ブラック・カルチャー 大西洋を旅する声と音」(岩波新書)
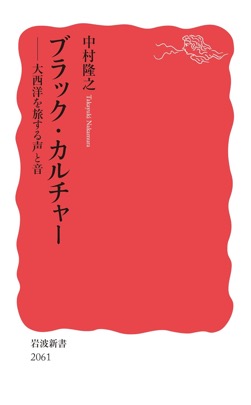
筆者はアメリカ合衆国のブラック・カルチャー専門家というよりは、カリブ海文学の専門家である。大変珍しい専門領域をお持ちのようだが、的確にアメリカ大陸全般のブラック・カルチャーの形成や展開を新書の中でまとめている。特にアメリカ大陸でのアフリカ系民族の奴隷制度との関連で、音楽だけでなく文学なども含めて理解する上では基礎的な内容になっているのだろう。ゴスペル、ジャズ、ソウル、ファンク、ヒップホップなどなど、ブラック・ミュージックを我々はジャンル分けしようとするが、それにはあまり意味はなく、根っこでいずれもが繋がっている。パン・アフリカニズムについて理解が深まったのが収穫だった。
・白井 聡・高瀬 毅(聞き手)「ニッポンの正体2025 世界の二極化と戦争の時代」(河出書房新社)
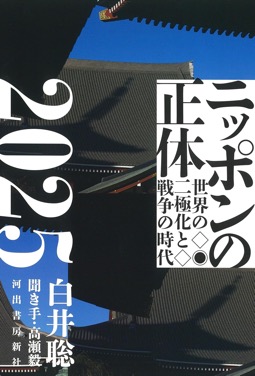
思想史家・政治学者で京都精華大学准教授の白井聡と、ジャーナリスト・ノンフィクション作家の高瀬毅との対談シリーズの最新作。白井の発言はときどき過激なものがあってドキッとする。
話題は国内政治状況(参院選を挟んで読んでいたので大変リアリティがあった)、東京一極集中、「戦後レジーム」について、大学の来し方行く末、労働について、「公助」の崩壊、朝鮮半島有事についてなど、多岐にわたっているが、最後の朝鮮半島有事については韓国の政権交代以前、トランプ再選以前の対談であり、現実が本の中の予測を追い越してしまっているので、賞味期限切れに近い。
全体として非常にわかりやすく、集中すれば数日間で読める。
・吉田 修一著「国宝 上」(朝日新聞出版)
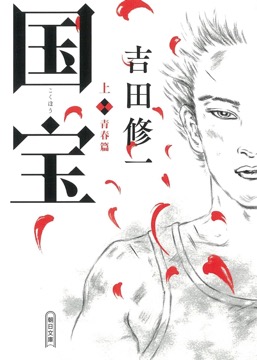
まず映画を鑑賞して、原作を読みたくなり、買い求めた。小説を読むのは実に久しぶりである。映画では描けなかった部分が描かれていて、一気にのめり込んだ。映画では描ききれなかった部分は複数あるのだが、ここで書いてしまっては元も子もないので書かないでおく。映画を観た後に読んでも、原作を先に読んで映画を観に行ってもどちらも楽しめるだろう。文体が「でございます。」というのも非常に珍しく、ユニークであった。上下巻だが、今月中に下巻まで読み切ることは難しかった。
上巻の後半は、主人公喜久雄の役者人生の中での天国と地獄が描かれる。映画では見られなかった、周辺人物や企業からのねちっこいいじめがすさまじい。
・黒田 明伸著「歴史の中の貨幣 銅銭がつないだ東アジア」(岩波新書)
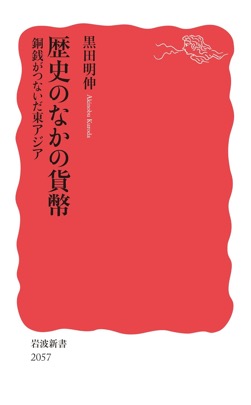
「国宝 上」と平行して月末から読み始めた。これがまたとても面白い内容だった。東アジアの銅銭として最も古いのは秦の半両銭、前漢の五銖銭であり、日本でも和同開珎以後「皇朝十二銭」が発行されてきた、というのが大学受験を前提とした貨幣史の基礎である。
だが、中国でも日本でも、貨幣経済がそのまま右肩上がりに進むのではなく、銅銭の製造に必要な銅鉱石の資源供給や精錬技術のハードルがあり、銅銭の品位の問題や流通範囲の限定などの結果、基本的には高額なもの(土地など)の対価としては絹や麻の布が用いられてきた。日本では、皇朝十二銭以後、戦国時代末期に至るまで自国で鋳造された貨幣は存在せず、中国から流入した銅銭が用いられ、銅銭は鋳つぶされて仏像や梵鐘などに再利用された。
租庸調をはじめ、銭納原則だった両税法でも現実には物納が行われてきた。それが宋代になって精練法の向上によって銅銭が大量発行され、交子や会子という手形から生まれた紙幣すら流通するようになった。このころ、大量に銅銭は日本にもたらされる。
元代になると、紙幣が主要通貨となり、原則中国では銅貨が使用できなくなる。これも大変ユニークなところ。明代初期も同様だが、紙幣のみの貨幣経済が一元的に行われたわけではない。かたや日本では15世紀に精錬技術が飛躍的に向上して銅生産が拡大し、銅は日明貿易(勘合貿易)や倭寇によって中国やヴェトナムに流入する。同じころ、永楽通宝といわれる銅貨が登場するが、日本との貿易にもっぱら使われ、明ではあまり流通せず、しかも私鋳が行われてきた。銅貨を取り巻く状況は非常に複雑で渾沌としていたのである。やがて明末に銀が登場するが、銀はあくまで秤量貨幣であって計数貨幣ではない。一般民衆が手にできるものではなく、末端では銅貨が用いられてきた。
撰銭だとか、貫高制から石高制への転換が室町・戦国時代を通じて日本では行われるが、かつて日本史の授業でならったこれらがいまひとつ腑に落ちないのは、「あとがき」の冒頭で筆者が書いている通りである。多くの人がいまだに完全に理解できていないのではないだろうか?筆者は長年の研究で端的な言葉で説明しているが、この本を読んでも筆者の理解に到達することは難しい。
というように、内容はなかなか難しいのだが、とても興味を引く問題が目白押しだった。特に第6章「貨幣システムと渡来銭」は貨幣制度そのものの理解に新しい視角を与えてくれる。
・石塚 真一著「BLUE GIANT MOMENTUM(5)」(小学館 ビッグコミックススペシャル)
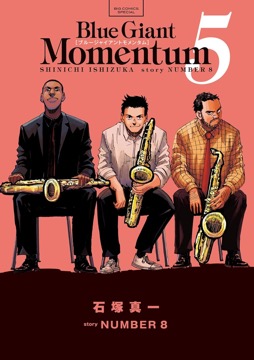
主人公のダイは、バンドメンバーのいるニューヨークを離れ、インターナショナル・ジャズ・コンペティションの行われるミズーリ州セントルイスに単身やってくる。そこで名うての若手サックスプレイヤーと競うべく、定められた10分の演奏を行う。予選を勝ち抜けるのは3人だけ…漫画のストーリーを細かく書くことはしたくないので短いがここまで。
・惣領 冬実著「カンツォニエーレ チェーザレ番外編」(コミックdays 講談社)
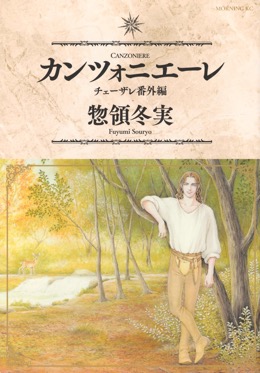
「チェーザレ 破壊の創造者」が13巻でストップしているが、これは本編からのスピンオフ作品。とはいえ、続編のようにも見える。「チェーザレ」第13巻で教皇選挙が行われた後、チェーザレの実父、ロドリーゴが教皇に就任し、チェーザレも枢機卿に任じられる。その時のチェーザレの秘めた恋についてが主題となっている。カンツォニエーレとは、ペトラルカの「抒情詩集」のイタリア語名。
相変わらず絵はきれいだし、惣領冬実が身を削って描いているのが想像できる。
この「チェーザレ」、本編はどうにも終わりそうにないが、スピンオフ作品でその空白を埋めていくのだろうか…
2025年4〜6月に読んだ本
2025/06/16 Mon Filed in: 読んだ本
・藤川 直也著「誤解を招いたとしたら申し訳ない 政治の言葉/言葉の政治」(講談社現代選書メチエ)
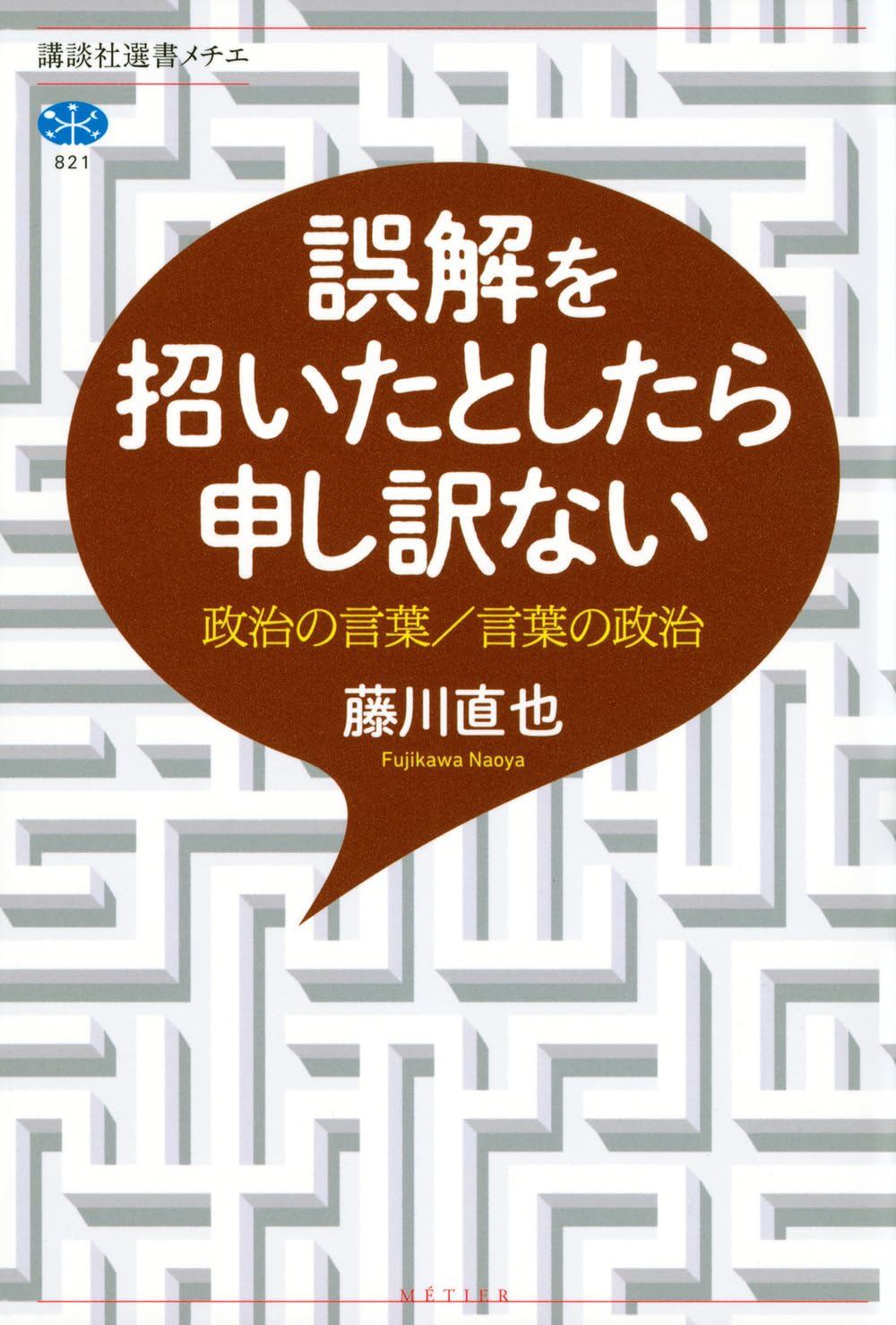
政治家の言葉はずいぶん空しいものに成り下がってしまった。まともな感受性ではああいった木で鼻を括ったような言葉は出てこないと思うのだが、平気であり得ない発言を繰り返し、「それは切り取りだ」「真意と異なる」などとうそぶく。どう切り取られようが、揺るがない自分の言葉の真意は残るはずである。調子に乗ってたとえ話をした部分が問題視されるということは、切り取りによるその政治家の真意とはほど遠い主張と考えるべきではなく、普段からその例えのようなことを考えているからついアドリブで真意が現れてくるのである。「誤解を招いたとしたら」などという、発言を聞いた相手に瑕疵があるような発言は言うだけ空しい。
言葉を大切にできない政治家は無用である。選挙でバンバン落とせばいい。
そんな空しい言葉の含意を、論理学を用いて精密に批判していくのが本書だが、理屈っぽすぎてなかなか頭に言葉が入ってこない。これは私の言葉への感受性が低いのか、論理的理解力がないのかわからないが、もっと一般人にわかるような書き方はできなかったのだろうか?著者はこれでも一般人のレベルまで下りてきて書いているらしいのだが・・
・佐々木 太郎著「コミンテルン 国際共産主義運動とは何だったのか」(中公新書)

タイトル通り、第3インターナショナルとも呼ばれたコミンテルン(国際共産主義の組織)について書かれた本である。非常に具体的で、わかりやすい本だった。ロシア革命後、革命家たちは「世界革命論」に依拠して他のヨーロッパ諸国での社会主義革命に期待した。農業国ロシアだけでは真の社会主義が建設できないと考え、ドイツのような先進国での社会主義革命と連携することが期待されたのである。しかしドイツ革命は第一次世界大戦でのドイツ降伏時に起こったが失敗に帰し、ヴァイマール体制が生まれる。結局コミンテルン大会はヨーロッパの共産党からの代表者の大会にはならず、むしろ社会主義ソヴィエトの指令を受けて植民地からの自立を目指すアジア諸地域の共産主義者が集う大会になった。
中国共産党の初期段階や日本共産党にもコミンテルンは影響力を持ち、スターリン体制を支える国際組織になっていく。
こういう社会主義の歴史をコミンテルンを軸に捉えるには絶好の本だった。
・川端 美季著「風呂と愛国 『清潔な国民』はいかに生まれたか」(NHK出版新書)
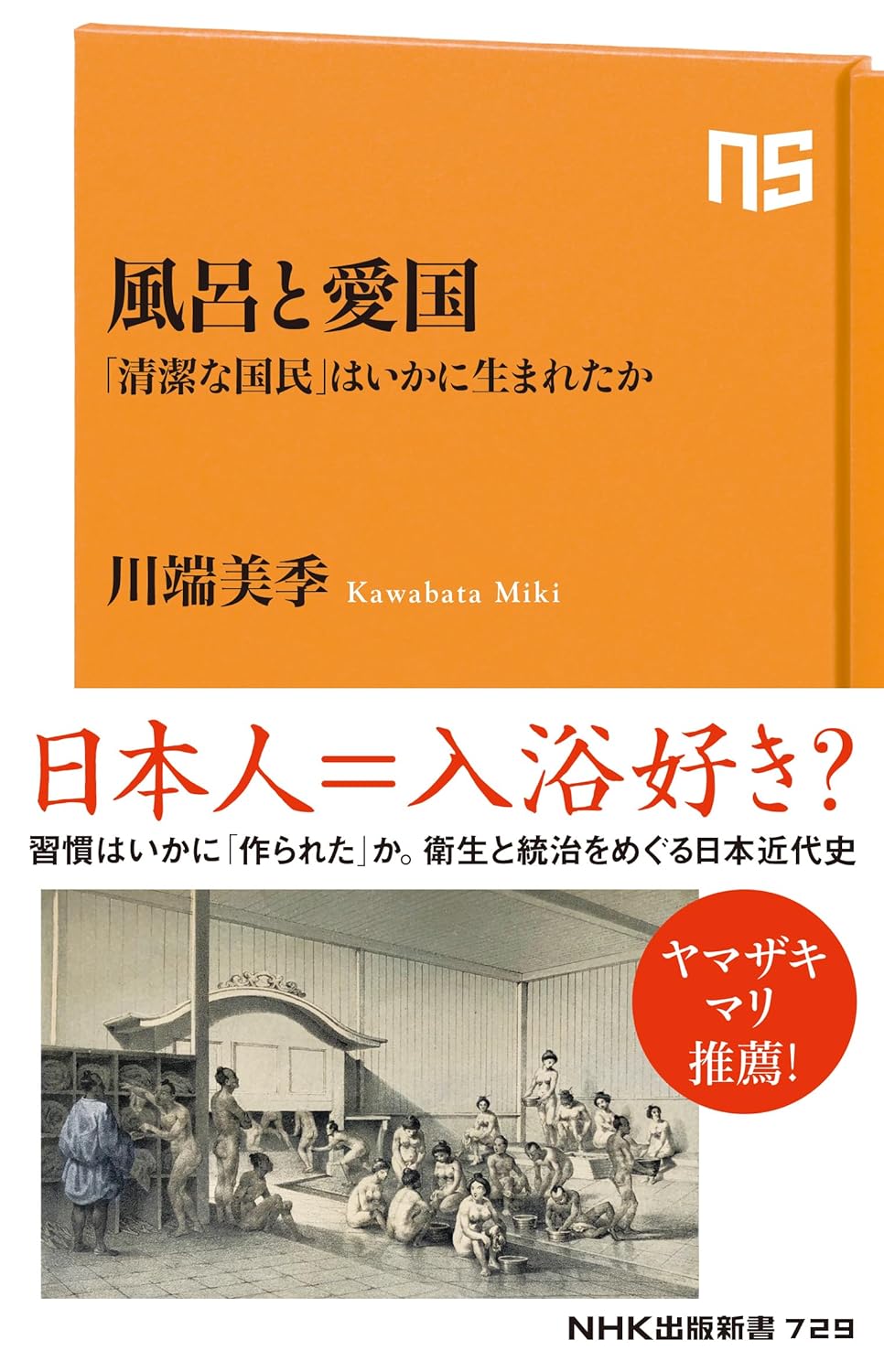
「風呂」と「愛国」という一見無関係な両者を繋ぎあわせようとする内容だが、読んでいてところどころ首をかしげたくなる箇所が散見された。定期的にシャワーではなく風呂に入る習慣が日本人の国民性にすり替えられていくところはわかるのだが、潔癖性や自裁行為と結びつくのはどうしてなのでろうか。教育上の「修身」と結びつける部分での教育史の著述が多い割には風呂そのものとの結びつきが弱い文章が続くのは、やはり論拠が弱いからではないだろうか?
なかなか両者を論理的に結びつけるには無理があるように感じられてならない。
もう1つ、電子版で読んだが、全体の60%で本文が終わってしまったのJは残念である。その分註は多いのだが・・
・伊藤 将人著「移動と階級 人生は移動距離で決まるのか」(講談社現代新書)
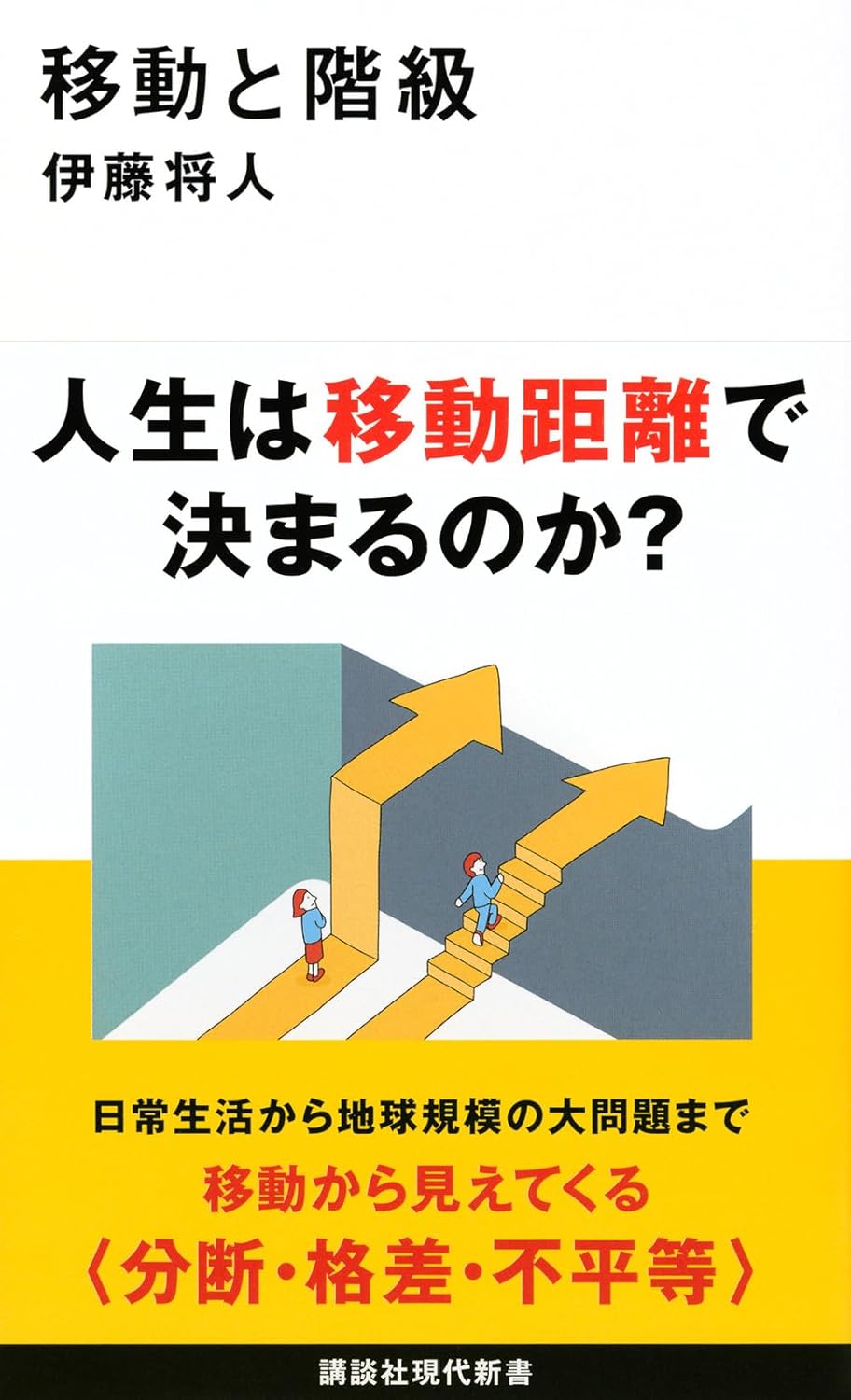
何気なく毎日している「移動」。その側面をあらためて掘り下げている。移動ができる人、長距離移動を何の心理的障壁もなくできる人は裕福で特権的階級であり、多くの人々はそこまで遠距離の移動を繰り返さない、というところは東京という都会に住んでいるとなかなか自覚できないことだ。
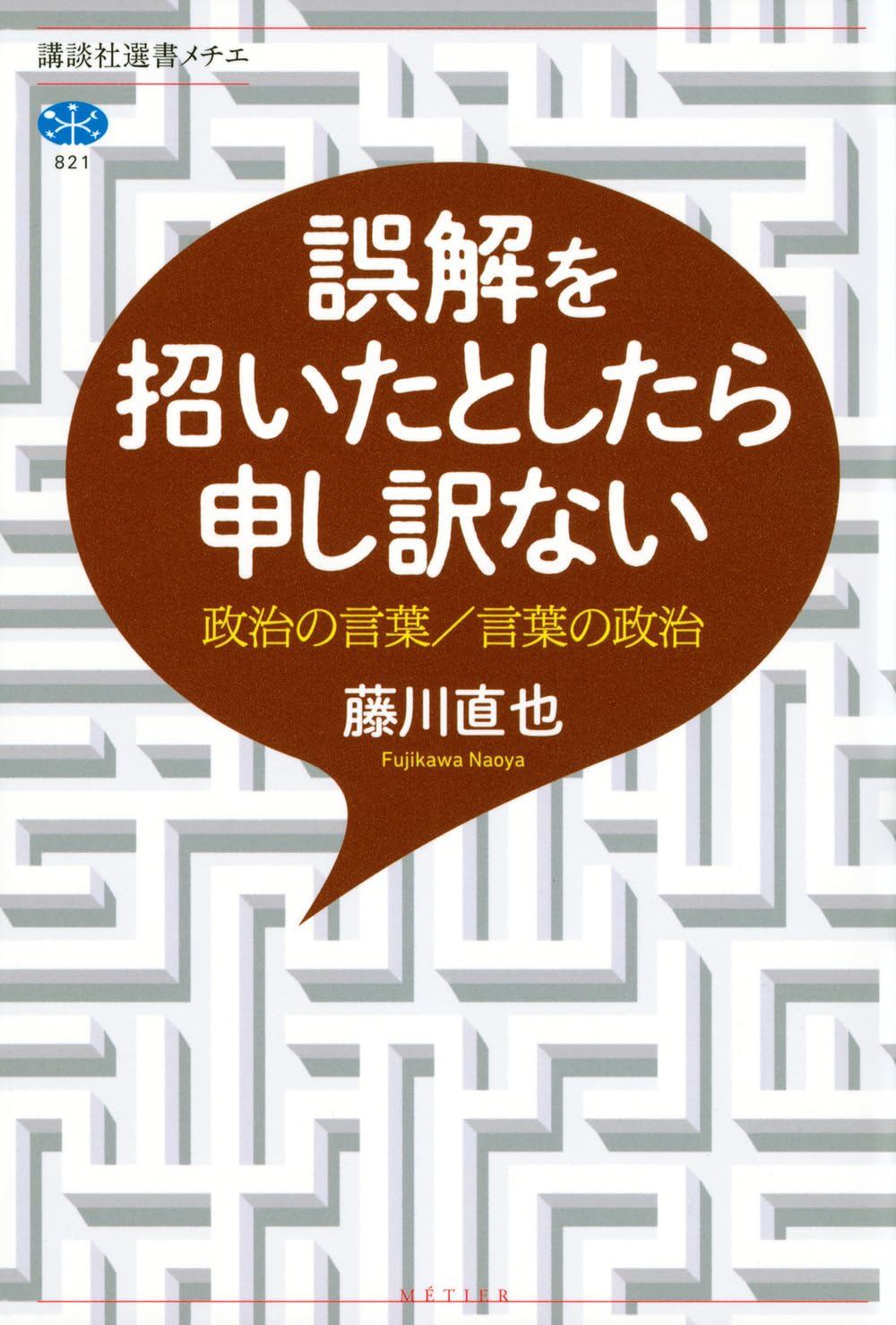
政治家の言葉はずいぶん空しいものに成り下がってしまった。まともな感受性ではああいった木で鼻を括ったような言葉は出てこないと思うのだが、平気であり得ない発言を繰り返し、「それは切り取りだ」「真意と異なる」などとうそぶく。どう切り取られようが、揺るがない自分の言葉の真意は残るはずである。調子に乗ってたとえ話をした部分が問題視されるということは、切り取りによるその政治家の真意とはほど遠い主張と考えるべきではなく、普段からその例えのようなことを考えているからついアドリブで真意が現れてくるのである。「誤解を招いたとしたら」などという、発言を聞いた相手に瑕疵があるような発言は言うだけ空しい。
言葉を大切にできない政治家は無用である。選挙でバンバン落とせばいい。
そんな空しい言葉の含意を、論理学を用いて精密に批判していくのが本書だが、理屈っぽすぎてなかなか頭に言葉が入ってこない。これは私の言葉への感受性が低いのか、論理的理解力がないのかわからないが、もっと一般人にわかるような書き方はできなかったのだろうか?著者はこれでも一般人のレベルまで下りてきて書いているらしいのだが・・
・佐々木 太郎著「コミンテルン 国際共産主義運動とは何だったのか」(中公新書)

タイトル通り、第3インターナショナルとも呼ばれたコミンテルン(国際共産主義の組織)について書かれた本である。非常に具体的で、わかりやすい本だった。ロシア革命後、革命家たちは「世界革命論」に依拠して他のヨーロッパ諸国での社会主義革命に期待した。農業国ロシアだけでは真の社会主義が建設できないと考え、ドイツのような先進国での社会主義革命と連携することが期待されたのである。しかしドイツ革命は第一次世界大戦でのドイツ降伏時に起こったが失敗に帰し、ヴァイマール体制が生まれる。結局コミンテルン大会はヨーロッパの共産党からの代表者の大会にはならず、むしろ社会主義ソヴィエトの指令を受けて植民地からの自立を目指すアジア諸地域の共産主義者が集う大会になった。
中国共産党の初期段階や日本共産党にもコミンテルンは影響力を持ち、スターリン体制を支える国際組織になっていく。
こういう社会主義の歴史をコミンテルンを軸に捉えるには絶好の本だった。
・川端 美季著「風呂と愛国 『清潔な国民』はいかに生まれたか」(NHK出版新書)
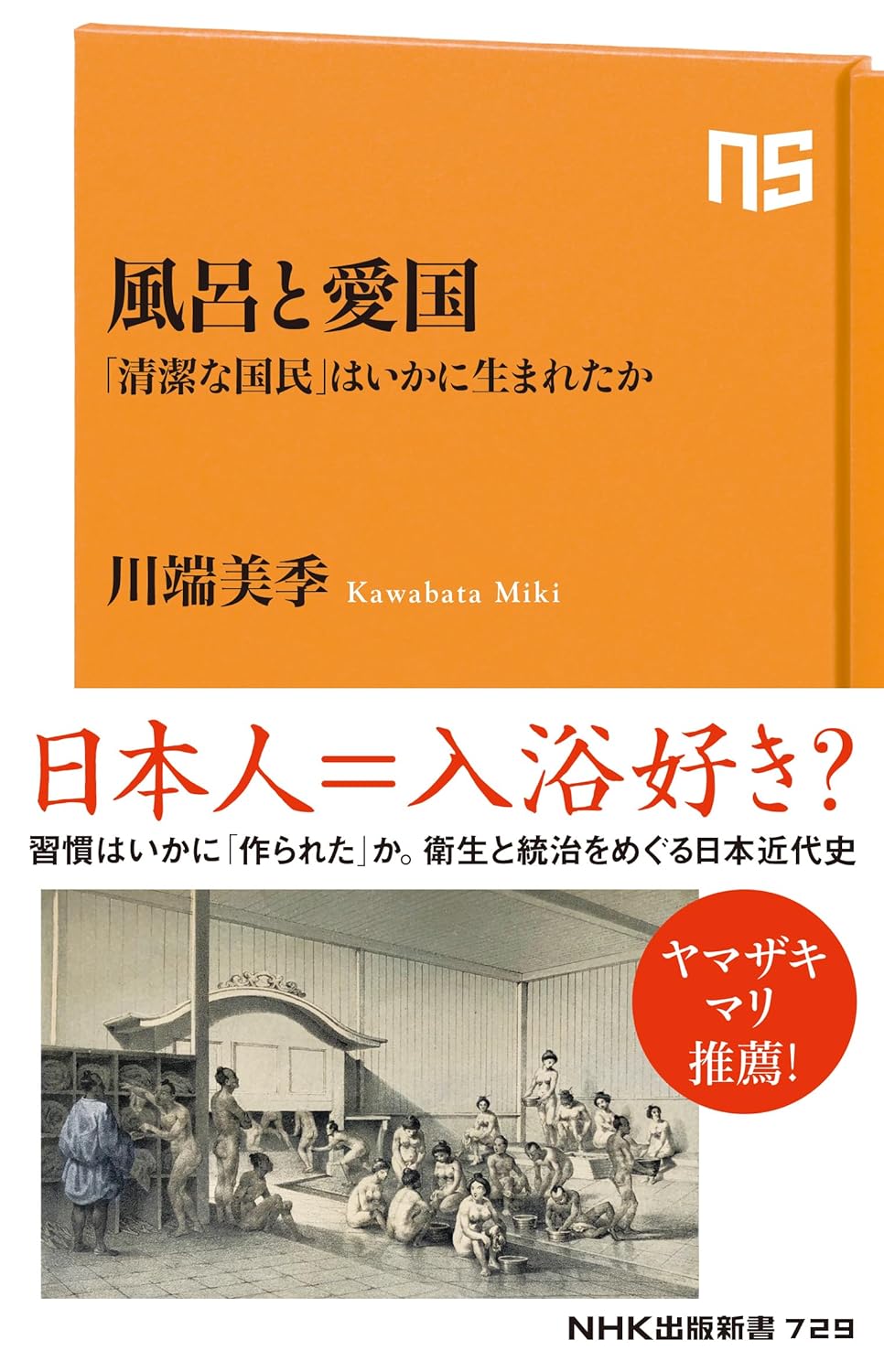
「風呂」と「愛国」という一見無関係な両者を繋ぎあわせようとする内容だが、読んでいてところどころ首をかしげたくなる箇所が散見された。定期的にシャワーではなく風呂に入る習慣が日本人の国民性にすり替えられていくところはわかるのだが、潔癖性や自裁行為と結びつくのはどうしてなのでろうか。教育上の「修身」と結びつける部分での教育史の著述が多い割には風呂そのものとの結びつきが弱い文章が続くのは、やはり論拠が弱いからではないだろうか?
なかなか両者を論理的に結びつけるには無理があるように感じられてならない。
もう1つ、電子版で読んだが、全体の60%で本文が終わってしまったのJは残念である。その分註は多いのだが・・
・伊藤 将人著「移動と階級 人生は移動距離で決まるのか」(講談社現代新書)
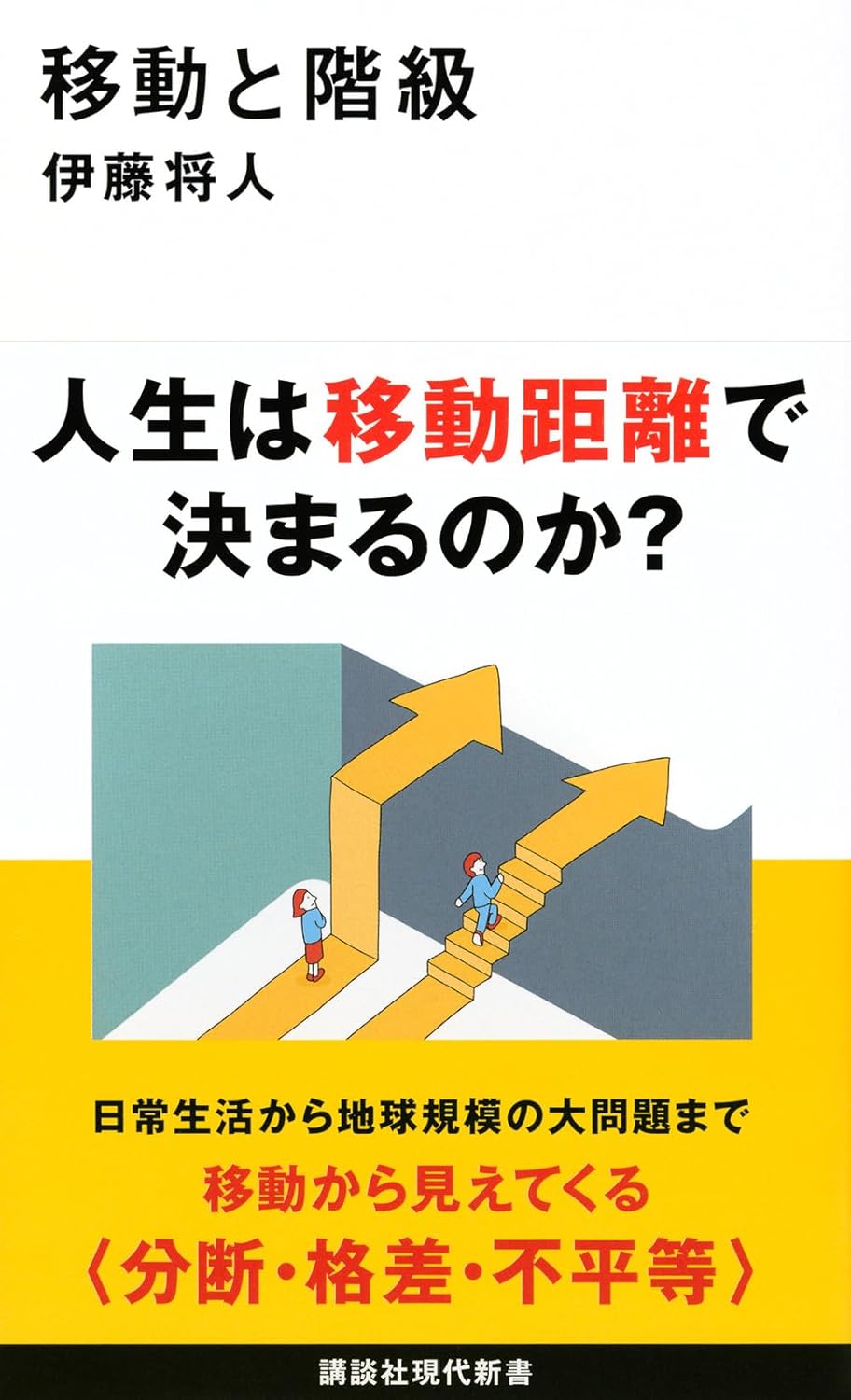
何気なく毎日している「移動」。その側面をあらためて掘り下げている。移動ができる人、長距離移動を何の心理的障壁もなくできる人は裕福で特権的階級であり、多くの人々はそこまで遠距離の移動を繰り返さない、というところは東京という都会に住んでいるとなかなか自覚できないことだ。
