2025年4〜6月に読んだ本
2025/06/16 Mon Filed in: 読んだ本
・藤川 直也著「誤解を招いたとしたら申し訳ない 政治の言葉/言葉の政治」(講談社現代選書メチエ)
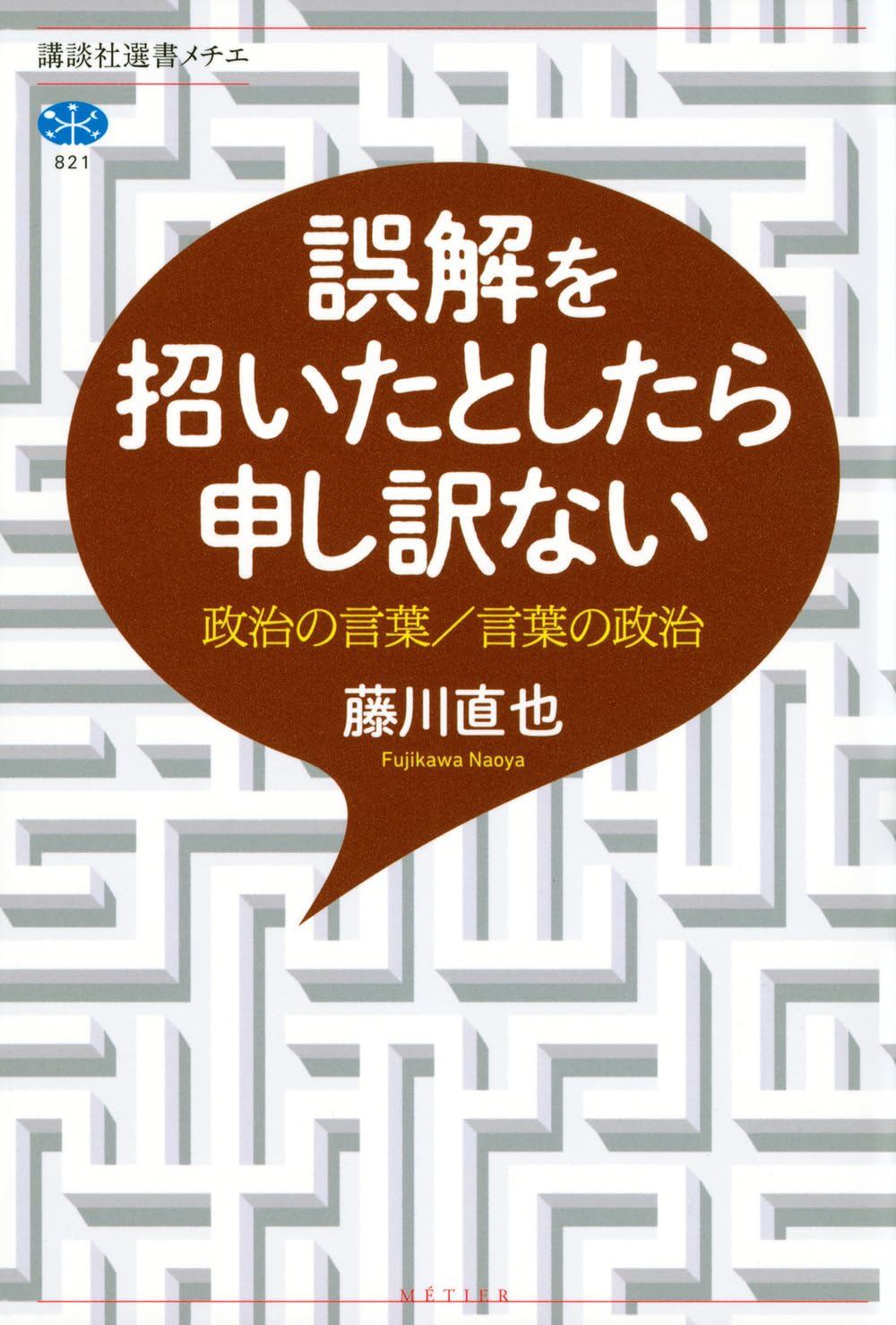
政治家の言葉はずいぶん空しいものに成り下がってしまった。まともな感受性ではああいった木で鼻を括ったような言葉は出てこないと思うのだが、平気であり得ない発言を繰り返し、「それは切り取りだ」「真意と異なる」などとうそぶく。どう切り取られようが、揺るがない自分の言葉の真意は残るはずである。調子に乗ってたとえ話をした部分が問題視されるということは、切り取りによるその政治家の真意とはほど遠い主張と考えるべきではなく、普段からその例えのようなことを考えているからついアドリブで真意が現れてくるのである。「誤解を招いたとしたら」などという、発言を聞いた相手に瑕疵があるような発言は言うだけ空しい。
言葉を大切にできない政治家は無用である。選挙でバンバン落とせばいい。
そんな空しい言葉の含意を、論理学を用いて精密に批判していくのが本書だが、理屈っぽすぎてなかなか頭に言葉が入ってこない。これは私の言葉への感受性が低いのか、論理的理解力がないのかわからないが、もっと一般人にわかるような書き方はできなかったのだろうか?著者はこれでも一般人のレベルまで下りてきて書いているらしいのだが・・
・佐々木 太郎著「コミンテルン 国際共産主義運動とは何だったのか」(中公新書)

タイトル通り、第3インターナショナルとも呼ばれたコミンテルン(国際共産主義の組織)について書かれた本である。非常に具体的で、わかりやすい本だった。ロシア革命後、革命家たちは「世界革命論」に依拠して他のヨーロッパ諸国での社会主義革命に期待した。農業国ロシアだけでは真の社会主義が建設できないと考え、ドイツのような先進国での社会主義革命と連携することが期待されたのである。しかしドイツ革命は第一次世界大戦でのドイツ降伏時に起こったが失敗に帰し、ヴァイマール体制が生まれる。結局コミンテルン大会はヨーロッパの共産党からの代表者の大会にはならず、むしろ社会主義ソヴィエトの指令を受けて植民地からの自立を目指すアジア諸地域の共産主義者が集う大会になった。
中国共産党の初期段階や日本共産党にもコミンテルンは影響力を持ち、スターリン体制を支える国際組織になっていく。
こういう社会主義の歴史をコミンテルンを軸に捉えるには絶好の本だった。
・川端 美季著「風呂と愛国 『清潔な国民』はいかに生まれたか」(NHK出版新書)
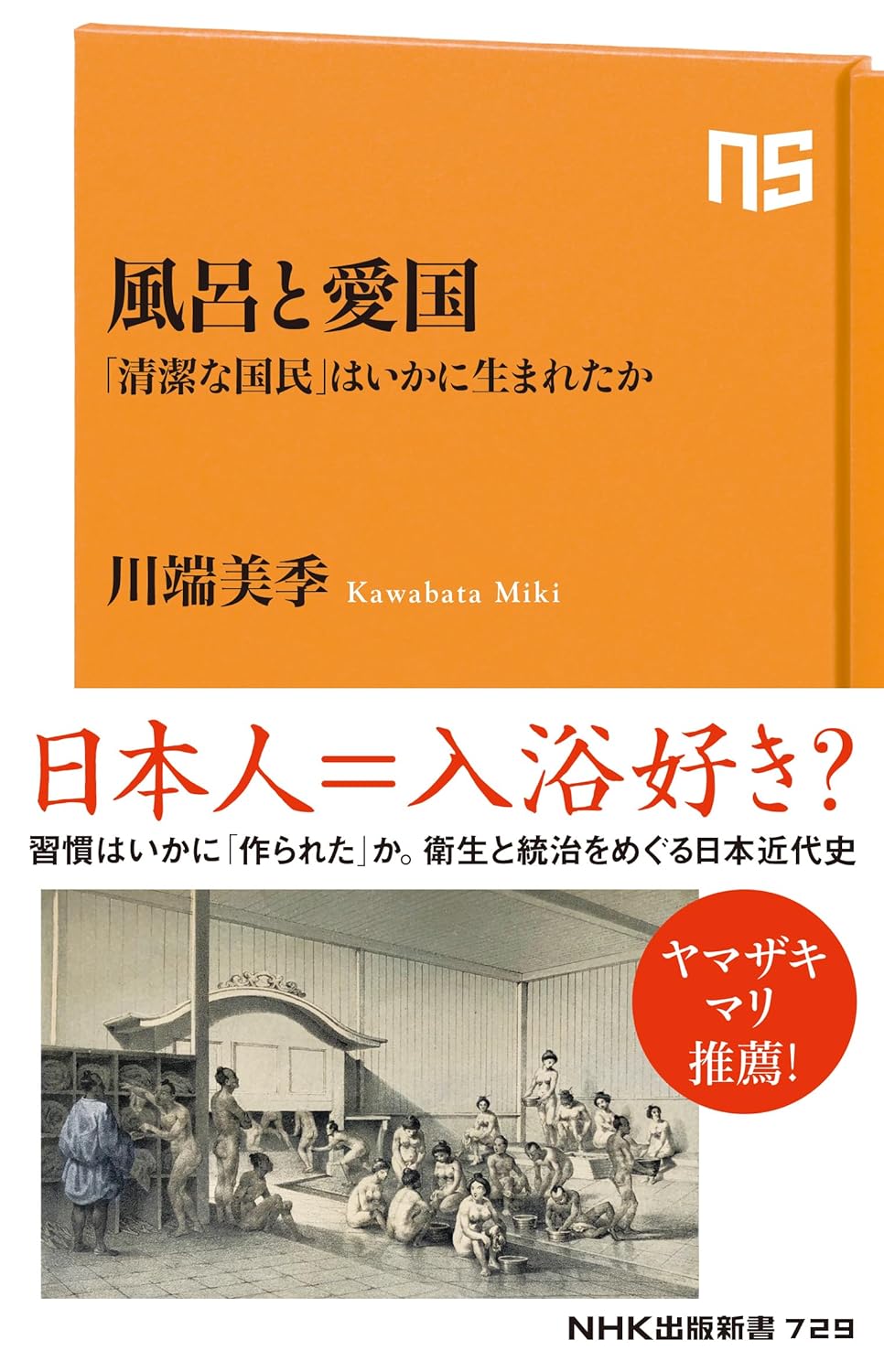
「風呂」と「愛国」という一見無関係な両者を繋ぎあわせようとする内容だが、読んでいてところどころ首をかしげたくなる箇所が散見された。定期的にシャワーではなく風呂に入る習慣が日本人の国民性にすり替えられていくところはわかるのだが、潔癖性や自裁行為と結びつくのはどうしてなのでろうか。教育上の「修身」と結びつける部分での教育史の著述が多い割には風呂そのものとの結びつきが弱い文章が続くのは、やはり論拠が弱いからではないだろうか?
なかなか両者を論理的に結びつけるには無理があるように感じられてならない。
もう1つ、電子版で読んだが、全体の60%で本文が終わってしまったのJは残念である。その分註は多いのだが・・
・伊藤 将人著「移動と階級 人生は移動距離で決まるのか」(講談社現代新書)
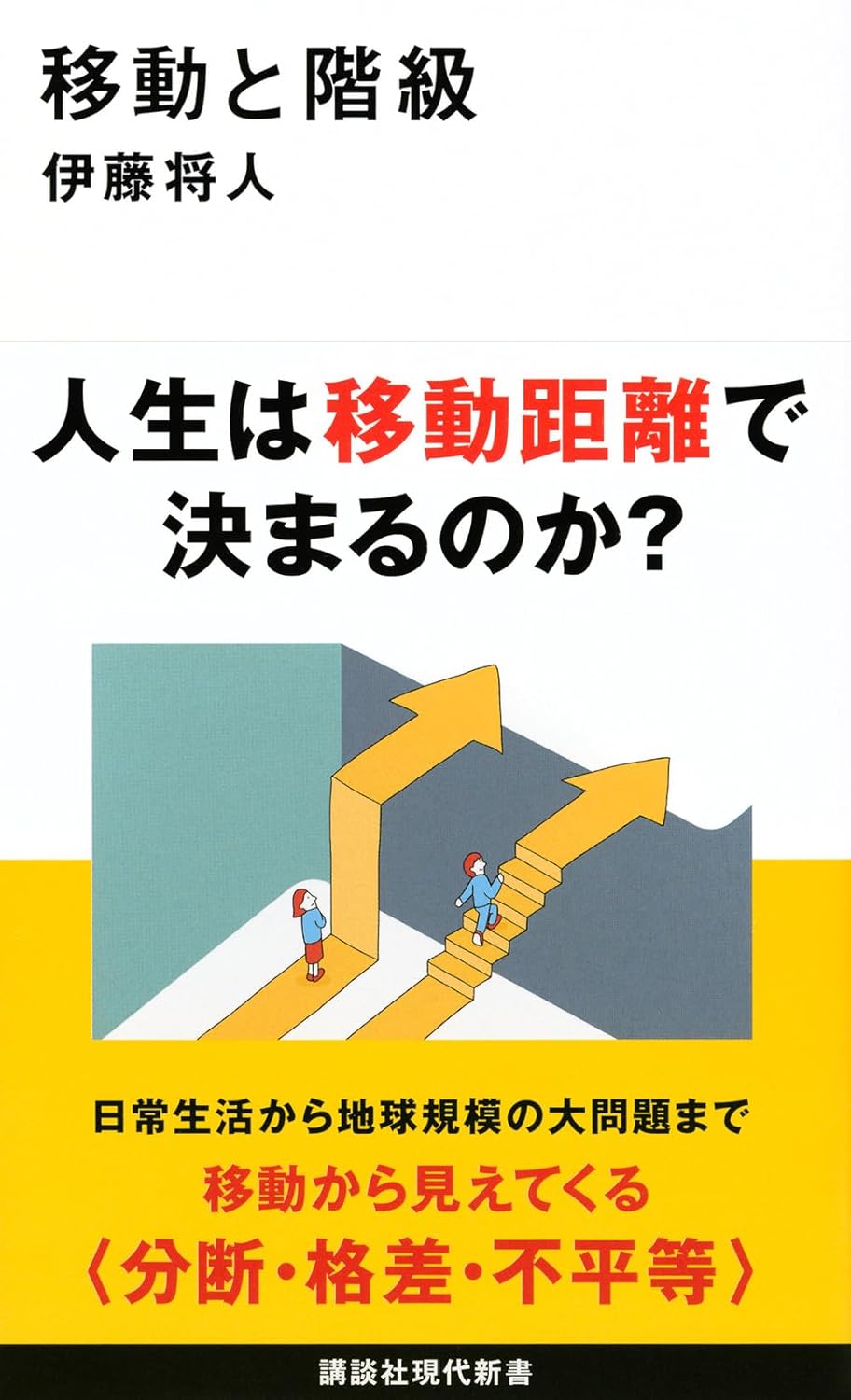
何気なく毎日している「移動」。その側面をあらためて掘り下げている。移動ができる人、長距離移動を何の心理的障壁もなくできる人は裕福で特権的階級であり、多くの人々はそこまで遠距離の移動を繰り返さない、というところは東京という都会に住んでいるとなかなか自覚できないことだ。
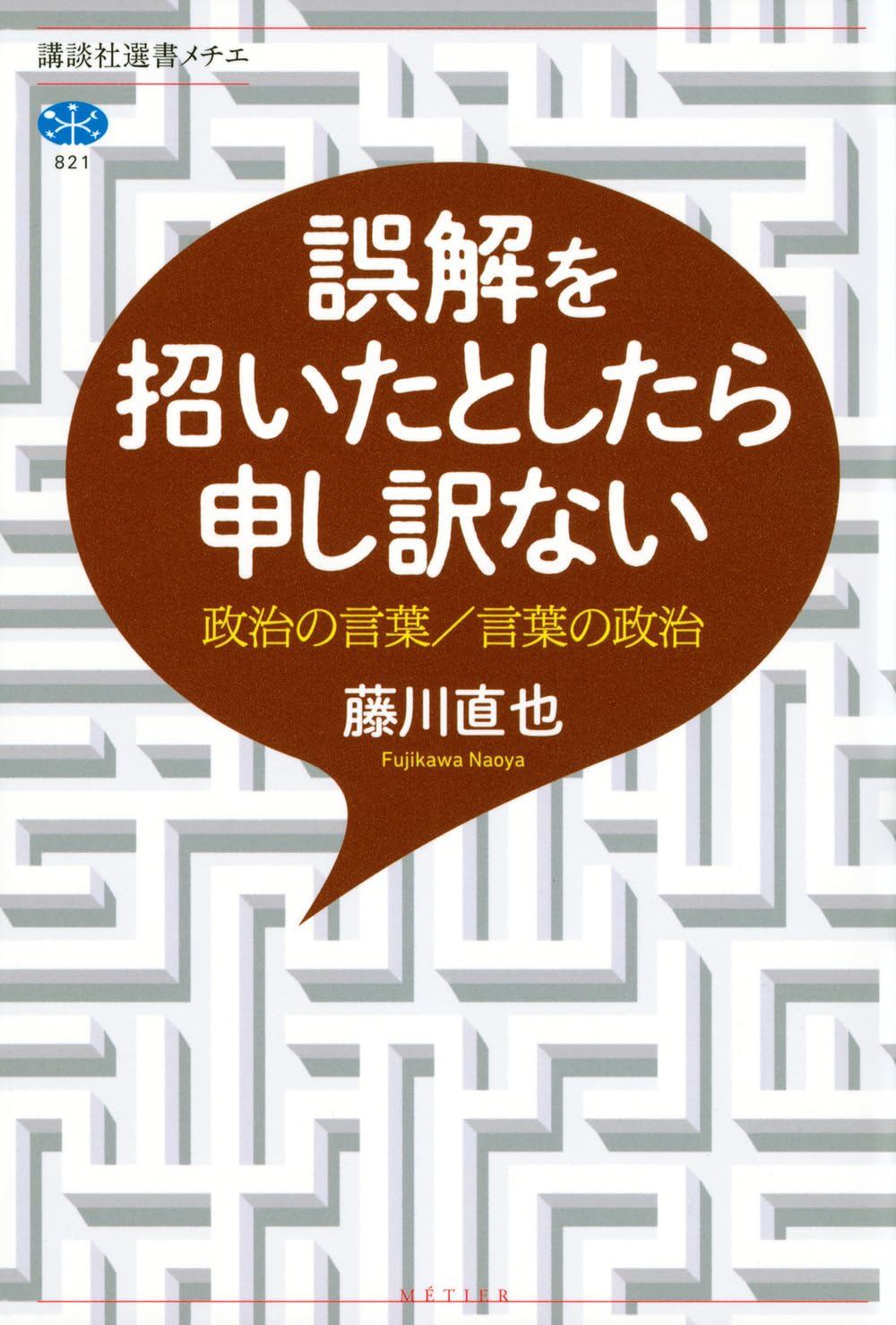
政治家の言葉はずいぶん空しいものに成り下がってしまった。まともな感受性ではああいった木で鼻を括ったような言葉は出てこないと思うのだが、平気であり得ない発言を繰り返し、「それは切り取りだ」「真意と異なる」などとうそぶく。どう切り取られようが、揺るがない自分の言葉の真意は残るはずである。調子に乗ってたとえ話をした部分が問題視されるということは、切り取りによるその政治家の真意とはほど遠い主張と考えるべきではなく、普段からその例えのようなことを考えているからついアドリブで真意が現れてくるのである。「誤解を招いたとしたら」などという、発言を聞いた相手に瑕疵があるような発言は言うだけ空しい。
言葉を大切にできない政治家は無用である。選挙でバンバン落とせばいい。
そんな空しい言葉の含意を、論理学を用いて精密に批判していくのが本書だが、理屈っぽすぎてなかなか頭に言葉が入ってこない。これは私の言葉への感受性が低いのか、論理的理解力がないのかわからないが、もっと一般人にわかるような書き方はできなかったのだろうか?著者はこれでも一般人のレベルまで下りてきて書いているらしいのだが・・
・佐々木 太郎著「コミンテルン 国際共産主義運動とは何だったのか」(中公新書)

タイトル通り、第3インターナショナルとも呼ばれたコミンテルン(国際共産主義の組織)について書かれた本である。非常に具体的で、わかりやすい本だった。ロシア革命後、革命家たちは「世界革命論」に依拠して他のヨーロッパ諸国での社会主義革命に期待した。農業国ロシアだけでは真の社会主義が建設できないと考え、ドイツのような先進国での社会主義革命と連携することが期待されたのである。しかしドイツ革命は第一次世界大戦でのドイツ降伏時に起こったが失敗に帰し、ヴァイマール体制が生まれる。結局コミンテルン大会はヨーロッパの共産党からの代表者の大会にはならず、むしろ社会主義ソヴィエトの指令を受けて植民地からの自立を目指すアジア諸地域の共産主義者が集う大会になった。
中国共産党の初期段階や日本共産党にもコミンテルンは影響力を持ち、スターリン体制を支える国際組織になっていく。
こういう社会主義の歴史をコミンテルンを軸に捉えるには絶好の本だった。
・川端 美季著「風呂と愛国 『清潔な国民』はいかに生まれたか」(NHK出版新書)
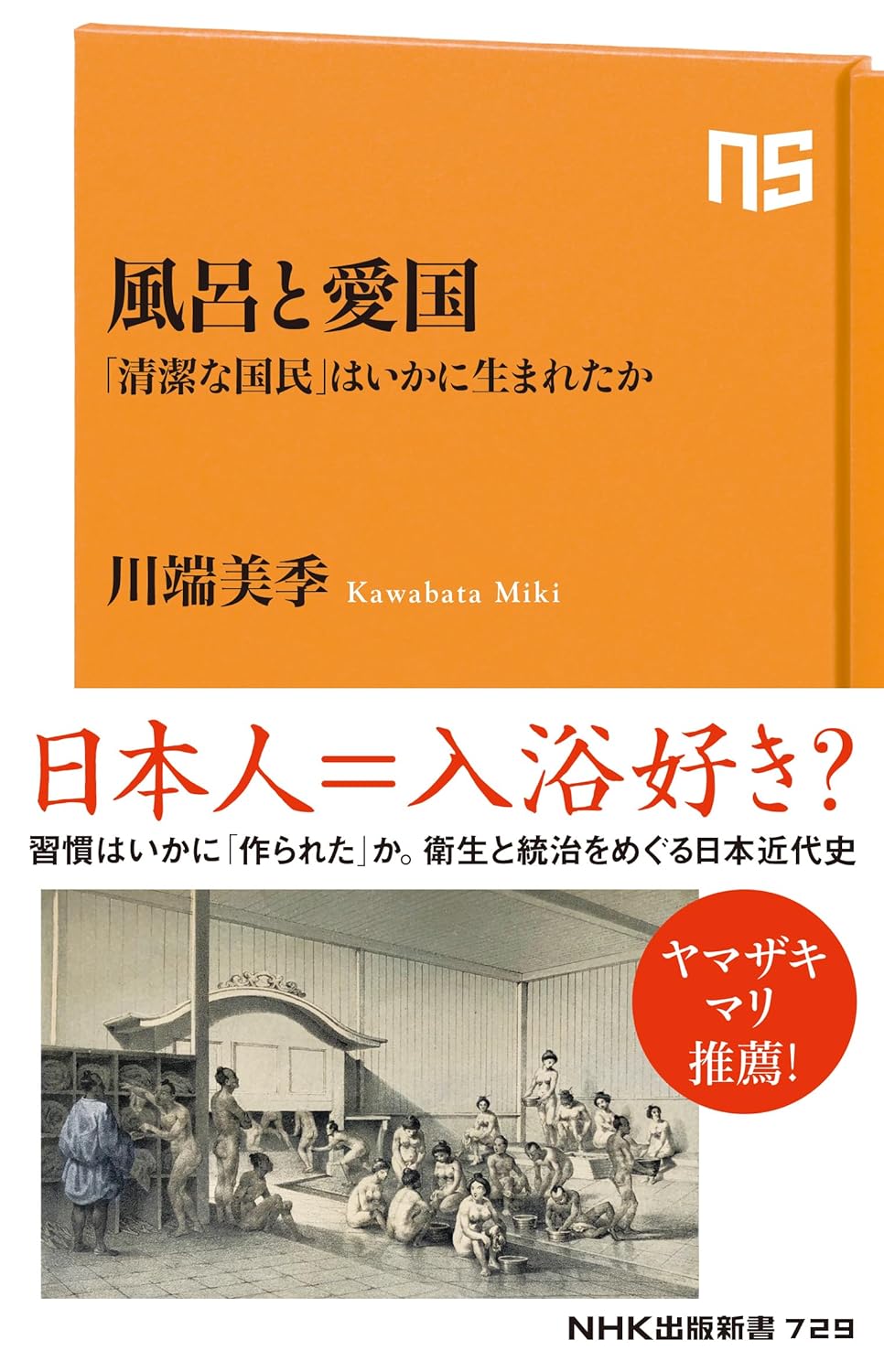
「風呂」と「愛国」という一見無関係な両者を繋ぎあわせようとする内容だが、読んでいてところどころ首をかしげたくなる箇所が散見された。定期的にシャワーではなく風呂に入る習慣が日本人の国民性にすり替えられていくところはわかるのだが、潔癖性や自裁行為と結びつくのはどうしてなのでろうか。教育上の「修身」と結びつける部分での教育史の著述が多い割には風呂そのものとの結びつきが弱い文章が続くのは、やはり論拠が弱いからではないだろうか?
なかなか両者を論理的に結びつけるには無理があるように感じられてならない。
もう1つ、電子版で読んだが、全体の60%で本文が終わってしまったのJは残念である。その分註は多いのだが・・
・伊藤 将人著「移動と階級 人生は移動距離で決まるのか」(講談社現代新書)
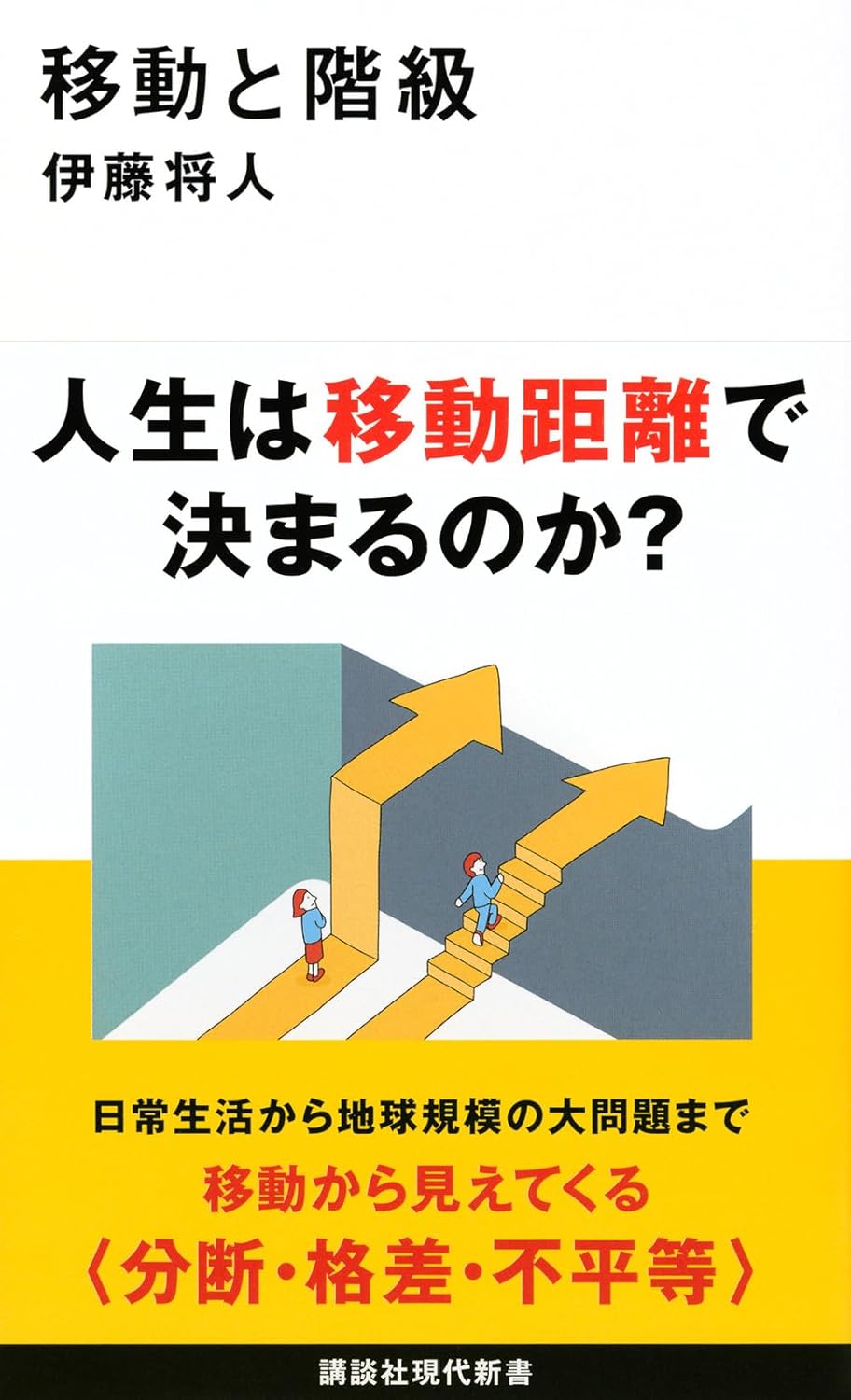
何気なく毎日している「移動」。その側面をあらためて掘り下げている。移動ができる人、長距離移動を何の心理的障壁もなくできる人は裕福で特権的階級であり、多くの人々はそこまで遠距離の移動を繰り返さない、というところは東京という都会に住んでいるとなかなか自覚できないことだ。
