August 2025
2025年8月に読んだ本
2025/08/12 Tue Filed in: 読んだ本
・吉田 修一著「国宝 下」(朝日新聞出版)
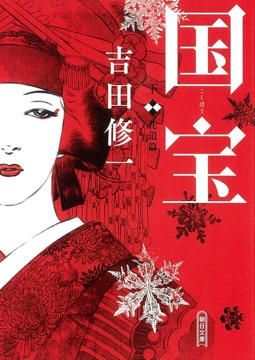
7月に読んだ上巻に続いて、下巻も読み終えた。映画も面白かったが、原作はさらに深みが増していて、映画をさらに複雑にした「深み」があった。実はこの小説の主人公は役者の喜久雄ではなく、喜久雄の影のようにふるまい、いつの間にか喜久雄の前から姿を消していた徳次(映画冒頭で座敷芸を喜久雄と演じていた、当時の喜久雄の兄貴分)ではないか、という気持ちにさせる。映画のほとんどはこの小説に忠実に、あるいは順序をずらして引用されたものだが、徳次や喜久雄の父親の死因については最後の最後まで伏線回収が成されないところが面白く、突然場面転換があってそこで書かれている内容を理解すると、急に腑に落ちるという構造になっている。
解説にある実際の歌舞伎の演目とこの小説との深い関連については、歌舞伎の知識がないだけに理解できず残念である。
・岩間 一弘著「中華料理と日本人 帝国主義から懐かしの味への100年史」(中公新書)
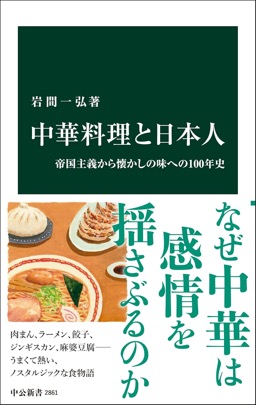
この本で取り上げられる中華料理(街の中華料理店やコンビニでポピュラーなメニュー)としては、肉まん、餃子、ウーロン茶、シュウマイ、ラーメン、麻婆豆腐である。
それぞれ私たちに馴染みの深い庶民的なもので、興味深く読んだが、本文が電子書籍の50%しかないのは残念。実に損した感じがする。
これが紙の本で半分しか本文がなく、のこりが全て注釈や参考文献だったらどうだろう?このような新書では、参考文献はもっと絞り込んで、内容を充実させるか、本一冊の価格を下げるべきだ。
・辻田 真佐憲著「『あの戦争』は何だったのか」(講談社現代新書)
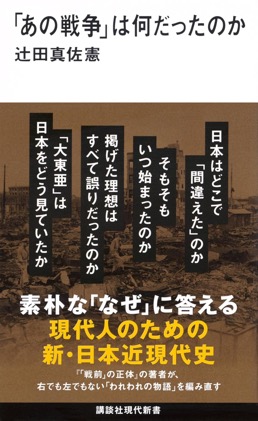
戦後80年の節目に読んでみた。辻田氏の著作は「戦前の正体」(講談社現代新書)を過去に読んでいる。
今回、日本が行ってきた戦争の呼称についての考察があり、興味深く読んだ。「太平洋戦争」「第二次世界大戦」「アジア・太平洋戦争」「十五年戦争」「大東亜戦争」などなど。石原莞爾の歴史観に従って江戸末期の開国が戦争への原点だという節も紹介してくれた。
そこで、辻田氏は「大東亜戦争」が最もふさわしいという個人的見解を持っているという。なかなか思い切った口上だが、誤解を与えかねない。
「大東亜戦争」の呼称は1941年の米英開戦によって戦争の呼称として東條内閣で閣議決定された呼称だが、戦後まもなくGHQから使用を禁じられ、独立以後も政府として使用しない方針は現在まで貫かれている(太平洋戦争も大東亜戦争も正式な法令上の定義はないという前提で)。「大東亜戦争」の呼称は、戦後は他の用語とフラットに扱うことができなかった経緯がある。かわりに歴史学界で用いられているのが「アジア・太平洋戦争」である。この呼称も本当にふさわしいかと言われれば、辻田氏の言うようにどこからも文句がつけられない「防衛的な」呼称と言われても仕方がない。
では辻田氏は敢えて「大東亜戦争」の呼称を積極的に用い広めようとしているのだろうか。そこに留意しながら先に読み進めていくと、最初に自ら「ふさわしい」と強調しておきながら、やや矛盾する記述が見られる。
例えば「大東亜戦争」=「日中戦争(支那事変とは呼んでいない)」+「太平洋戦争」と定義しているが、「1941年12月、大東亜戦争が勃発した」、と自らの定義から外れる当時の閣議決定に基づく戦争名称と開始時期を記述しているのは、時間軸と呼称に対する揺れが見られる一例である。
「大東亜」とは戦前の近衛内閣で登場した「東亜新秩序」「大東亜共栄圏」の構想を踏まえている(簡単に言えば東亜=日満支、大東亜=日満支を含み、東南アジア、や太平洋海域を含む、1941〜45年の戦闘地域全体)。資源欲しさに対外進出を強める口実となった2つの構想は、そもそも明確なビジョンに基づく構想ではない、ということを辻田氏は分析していく。そこは共感し理解できる。だが「『大東亜共栄圏』と言う用語は元来空疎」、と書きながら戦争名としては「大東亜戦争」がふさわしいといった書きっぷりは首をかしげたくなる。空疎な構想を土台とした戦争、という皮肉としてこの用語を用いるのであれば、そう宣言してから書いた方がいい。
また、歴史学と科学に対する見方にも私には疑問がある。「歴史は究極的に科学ではない、科学とはAとBという試薬を一定条件で混ぜれば必ずXという結果が得られるもの」、としているが、科学に対する理解が皮相的で一面的ではないだろうか。上のような主張は感覚的にはわかるものの、科学はそんなに単純なものではないはずだ。1つの結論だけが帰着点で、複数のプロセスが認められないというものでもなかろう。自然科学だって、大きなパラダイム転換を複数回繰り返してきた。歴史全体を揺るがすようなパラダイム転換はなかなか起こり得ないが、具体的な細部の見方についてはしょっちゅう変化し、既存の見方が覆されている。そういう意味では、歴史だって科学なのである。
合理的な分析と推論によって導かれた結論が「科学」を構成していて、その結論も観点の違いや批判によってより合理的で多数が納得できるような結論に置き換えられ得るもの、が科学的な学問だと私は思っている。自分の感情や都合、少数者の論証のない願望によって置き換えられるような結論は歴史的結論とは遠いところにある。
細かなことではあるが、「満州」ではなく「満洲」と正式な地名を書いているのに、東條英機については「東条」と略字を使っているのも気になる。子孫は「東條」を用いているのだから、そちらにあわせるべきであろう。
その他全体の記述については、納得できるものが多い。特に第4章で東條英機が「大東亜」各地を巡ったことにちなんで各地の歴史博物館などを筆者自らが訪れたことは非常に興味深く読むことができた。
・佐々木 俊尚著「歩くを楽しむ 自然を味わう フラット登山」(かんき出版)
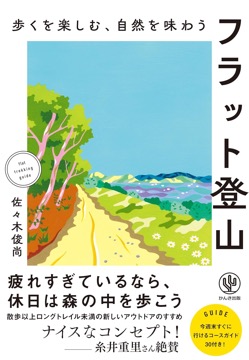
いま、ラジオなどで引っ張りだこの著者・著作である。山頂を目指さない登山をするというのは賛成する。最近はピークハントそのものが目的化しすぎていて、山全体を楽しむということが薄くなっている。百名山ハンターの登山スタイルは好きではないので、いっこうに百名山を完登することがない。自分の生活圏から遠く離れた山は、昔バイクツーリングのついでに登ったことがあるが、何度も行こうとは思わない。長野県の山々だって、県境の山は行ってみたいと思うこともあるが、夏山の混雑ぶりを考えると敬遠したくなる。できれば東北の山のように有人小屋がなく、避難小屋や静かなテント泊で生ける山がいいし、山全体を味わうには山頂だけがすべてではないはずだ。後半は具体的なフラット登山30コースが紹介されていて、四季に応じて歩けるルートが掲載されている。
上記の本のほか、昨年買ってなかなか読み進められなかった、安田浩一著「地震と虐殺 1923ー2024」もちょうど半分読んだが、来月に継続する。
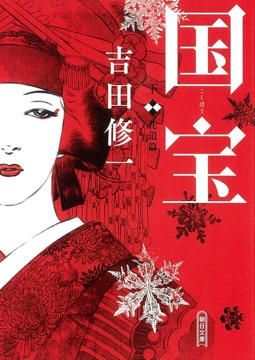
7月に読んだ上巻に続いて、下巻も読み終えた。映画も面白かったが、原作はさらに深みが増していて、映画をさらに複雑にした「深み」があった。実はこの小説の主人公は役者の喜久雄ではなく、喜久雄の影のようにふるまい、いつの間にか喜久雄の前から姿を消していた徳次(映画冒頭で座敷芸を喜久雄と演じていた、当時の喜久雄の兄貴分)ではないか、という気持ちにさせる。映画のほとんどはこの小説に忠実に、あるいは順序をずらして引用されたものだが、徳次や喜久雄の父親の死因については最後の最後まで伏線回収が成されないところが面白く、突然場面転換があってそこで書かれている内容を理解すると、急に腑に落ちるという構造になっている。
解説にある実際の歌舞伎の演目とこの小説との深い関連については、歌舞伎の知識がないだけに理解できず残念である。
・岩間 一弘著「中華料理と日本人 帝国主義から懐かしの味への100年史」(中公新書)
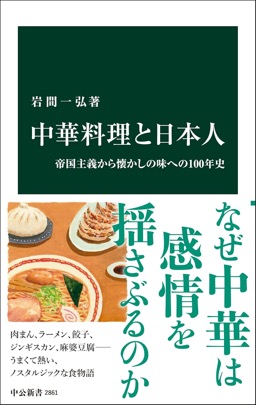
この本で取り上げられる中華料理(街の中華料理店やコンビニでポピュラーなメニュー)としては、肉まん、餃子、ウーロン茶、シュウマイ、ラーメン、麻婆豆腐である。
それぞれ私たちに馴染みの深い庶民的なもので、興味深く読んだが、本文が電子書籍の50%しかないのは残念。実に損した感じがする。
これが紙の本で半分しか本文がなく、のこりが全て注釈や参考文献だったらどうだろう?このような新書では、参考文献はもっと絞り込んで、内容を充実させるか、本一冊の価格を下げるべきだ。
・辻田 真佐憲著「『あの戦争』は何だったのか」(講談社現代新書)
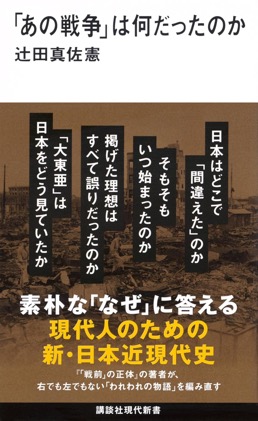
戦後80年の節目に読んでみた。辻田氏の著作は「戦前の正体」(講談社現代新書)を過去に読んでいる。
今回、日本が行ってきた戦争の呼称についての考察があり、興味深く読んだ。「太平洋戦争」「第二次世界大戦」「アジア・太平洋戦争」「十五年戦争」「大東亜戦争」などなど。石原莞爾の歴史観に従って江戸末期の開国が戦争への原点だという節も紹介してくれた。
そこで、辻田氏は「大東亜戦争」が最もふさわしいという個人的見解を持っているという。なかなか思い切った口上だが、誤解を与えかねない。
「大東亜戦争」の呼称は1941年の米英開戦によって戦争の呼称として東條内閣で閣議決定された呼称だが、戦後まもなくGHQから使用を禁じられ、独立以後も政府として使用しない方針は現在まで貫かれている(太平洋戦争も大東亜戦争も正式な法令上の定義はないという前提で)。「大東亜戦争」の呼称は、戦後は他の用語とフラットに扱うことができなかった経緯がある。かわりに歴史学界で用いられているのが「アジア・太平洋戦争」である。この呼称も本当にふさわしいかと言われれば、辻田氏の言うようにどこからも文句がつけられない「防衛的な」呼称と言われても仕方がない。
では辻田氏は敢えて「大東亜戦争」の呼称を積極的に用い広めようとしているのだろうか。そこに留意しながら先に読み進めていくと、最初に自ら「ふさわしい」と強調しておきながら、やや矛盾する記述が見られる。
例えば「大東亜戦争」=「日中戦争(支那事変とは呼んでいない)」+「太平洋戦争」と定義しているが、「1941年12月、大東亜戦争が勃発した」、と自らの定義から外れる当時の閣議決定に基づく戦争名称と開始時期を記述しているのは、時間軸と呼称に対する揺れが見られる一例である。
「大東亜」とは戦前の近衛内閣で登場した「東亜新秩序」「大東亜共栄圏」の構想を踏まえている(簡単に言えば東亜=日満支、大東亜=日満支を含み、東南アジア、や太平洋海域を含む、1941〜45年の戦闘地域全体)。資源欲しさに対外進出を強める口実となった2つの構想は、そもそも明確なビジョンに基づく構想ではない、ということを辻田氏は分析していく。そこは共感し理解できる。だが「『大東亜共栄圏』と言う用語は元来空疎」、と書きながら戦争名としては「大東亜戦争」がふさわしいといった書きっぷりは首をかしげたくなる。空疎な構想を土台とした戦争、という皮肉としてこの用語を用いるのであれば、そう宣言してから書いた方がいい。
また、歴史学と科学に対する見方にも私には疑問がある。「歴史は究極的に科学ではない、科学とはAとBという試薬を一定条件で混ぜれば必ずXという結果が得られるもの」、としているが、科学に対する理解が皮相的で一面的ではないだろうか。上のような主張は感覚的にはわかるものの、科学はそんなに単純なものではないはずだ。1つの結論だけが帰着点で、複数のプロセスが認められないというものでもなかろう。自然科学だって、大きなパラダイム転換を複数回繰り返してきた。歴史全体を揺るがすようなパラダイム転換はなかなか起こり得ないが、具体的な細部の見方についてはしょっちゅう変化し、既存の見方が覆されている。そういう意味では、歴史だって科学なのである。
合理的な分析と推論によって導かれた結論が「科学」を構成していて、その結論も観点の違いや批判によってより合理的で多数が納得できるような結論に置き換えられ得るもの、が科学的な学問だと私は思っている。自分の感情や都合、少数者の論証のない願望によって置き換えられるような結論は歴史的結論とは遠いところにある。
細かなことではあるが、「満州」ではなく「満洲」と正式な地名を書いているのに、東條英機については「東条」と略字を使っているのも気になる。子孫は「東條」を用いているのだから、そちらにあわせるべきであろう。
その他全体の記述については、納得できるものが多い。特に第4章で東條英機が「大東亜」各地を巡ったことにちなんで各地の歴史博物館などを筆者自らが訪れたことは非常に興味深く読むことができた。
・佐々木 俊尚著「歩くを楽しむ 自然を味わう フラット登山」(かんき出版)
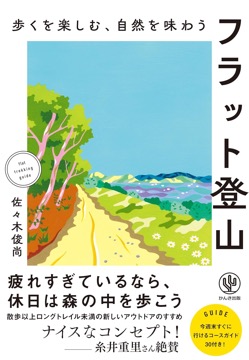
いま、ラジオなどで引っ張りだこの著者・著作である。山頂を目指さない登山をするというのは賛成する。最近はピークハントそのものが目的化しすぎていて、山全体を楽しむということが薄くなっている。百名山ハンターの登山スタイルは好きではないので、いっこうに百名山を完登することがない。自分の生活圏から遠く離れた山は、昔バイクツーリングのついでに登ったことがあるが、何度も行こうとは思わない。長野県の山々だって、県境の山は行ってみたいと思うこともあるが、夏山の混雑ぶりを考えると敬遠したくなる。できれば東北の山のように有人小屋がなく、避難小屋や静かなテント泊で生ける山がいいし、山全体を味わうには山頂だけがすべてではないはずだ。後半は具体的なフラット登山30コースが紹介されていて、四季に応じて歩けるルートが掲載されている。
上記の本のほか、昨年買ってなかなか読み進められなかった、安田浩一著「地震と虐殺 1923ー2024」もちょうど半分読んだが、来月に継続する。
