July 2025
2025年7月に読んだ本
2025/07/29 Tue Filed in: 読んだ本
・相田 豊著「愛と孤独のフォルクローレ ボリビア音楽家と生の人類学」(世界思想社)
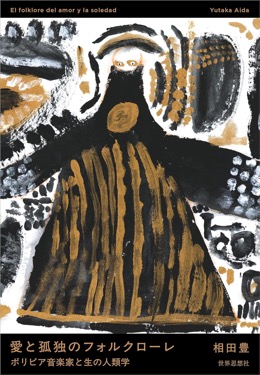
著者の相田さんは、実は私が一時だけ教えたことがあり、その後一時は同僚でもあった。彼は大学で中南米を対象とした人類学を専攻し、同好会でフォルクローレに魅せられ、フォルクローレ研究を進めてサンポーニャの演奏者にもなっているというユニークな研究者であり、現在は上智大学特任助教である。そのような学者がフィールドワークとしてボリビアの音楽家と交流し、文化人類学の論文とは異なるアプローチでこの大部な本を上梓した。博士論文を大幅にリライトしたものだそうだが、硬い論文の文体とは違い、一般読者にも実に読み易く、スルスルと内容がしみ渡ってくる。著者の逡巡も感じながら読んでいける。
・中村 隆之著「ブラック・カルチャー 大西洋を旅する声と音」(岩波新書)
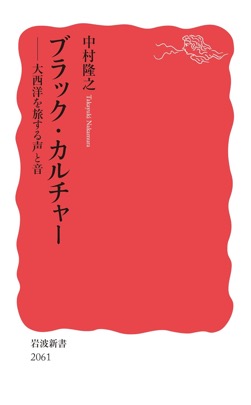
筆者はアメリカ合衆国のブラック・カルチャー専門家というよりは、カリブ海文学の専門家である。大変珍しい専門領域をお持ちのようだが、的確にアメリカ大陸全般のブラック・カルチャーの形成や展開を新書の中でまとめている。特にアメリカ大陸でのアフリカ系民族の奴隷制度との関連で、音楽だけでなく文学なども含めて理解する上では基礎的な内容になっているのだろう。ゴスペル、ジャズ、ソウル、ファンク、ヒップホップなどなど、ブラック・ミュージックを我々はジャンル分けしようとするが、それにはあまり意味はなく、根っこでいずれもが繋がっている。パン・アフリカニズムについて理解が深まったのが収穫だった。
・白井 聡・高瀬 毅(聞き手)「ニッポンの正体2025 世界の二極化と戦争の時代」(河出書房新社)
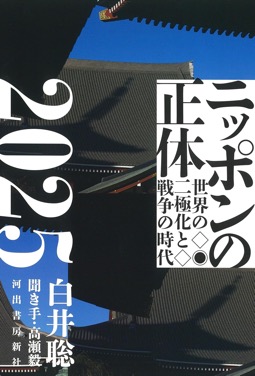
思想史家・政治学者で京都精華大学准教授の白井聡と、ジャーナリスト・ノンフィクション作家の高瀬毅との対談シリーズの最新作。白井の発言はときどき過激なものがあってドキッとする。
話題は国内政治状況(参院選を挟んで読んでいたので大変リアリティがあった)、東京一極集中、「戦後レジーム」について、大学の来し方行く末、労働について、「公助」の崩壊、朝鮮半島有事についてなど、多岐にわたっているが、最後の朝鮮半島有事については韓国の政権交代以前、トランプ再選以前の対談であり、現実が本の中の予測を追い越してしまっているので、賞味期限切れに近い。
全体として非常にわかりやすく、集中すれば数日間で読める。
・吉田 修一著「国宝 上」(朝日新聞出版)
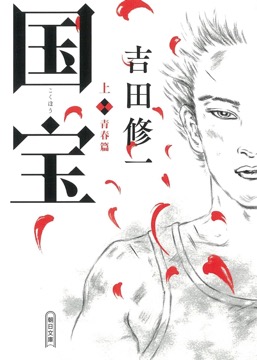
まず映画を鑑賞して、原作を読みたくなり、買い求めた。小説を読むのは実に久しぶりである。映画では描けなかった部分が描かれていて、一気にのめり込んだ。映画では描ききれなかった部分は複数あるのだが、ここで書いてしまっては元も子もないので書かないでおく。映画を観た後に読んでも、原作を先に読んで映画を観に行ってもどちらも楽しめるだろう。文体が「でございます。」というのも非常に珍しく、ユニークであった。上下巻だが、今月中に下巻まで読み切ることは難しかった。
上巻の後半は、主人公喜久雄の役者人生の中での天国と地獄が描かれる。映画では見られなかった、周辺人物や企業からのねちっこいいじめがすさまじい。
・黒田 明伸著「歴史の中の貨幣 銅銭がつないだ東アジア」(岩波新書)
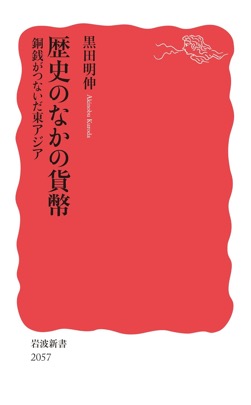
「国宝 上」と平行して月末から読み始めた。これがまたとても面白い内容だった。東アジアの銅銭として最も古いのは秦の半両銭、前漢の五銖銭であり、日本でも和同開珎以後「皇朝十二銭」が発行されてきた、というのが大学受験を前提とした貨幣史の基礎である。
だが、中国でも日本でも、貨幣経済がそのまま右肩上がりに進むのではなく、銅銭の製造に必要な銅鉱石の資源供給や精錬技術のハードルがあり、銅銭の品位の問題や流通範囲の限定などの結果、基本的には高額なもの(土地など)の対価としては絹や麻の布が用いられてきた。日本では、皇朝十二銭以後、戦国時代末期に至るまで自国で鋳造された貨幣は存在せず、中国から流入した銅銭が用いられ、銅銭は鋳つぶされて仏像や梵鐘などに再利用された。
租庸調をはじめ、銭納原則だった両税法でも現実には物納が行われてきた。それが宋代になって精練法の向上によって銅銭が大量発行され、交子や会子という手形から生まれた紙幣すら流通するようになった。このころ、大量に銅銭は日本にもたらされる。
元代になると、紙幣が主要通貨となり、原則中国では銅貨が使用できなくなる。これも大変ユニークなところ。明代初期も同様だが、紙幣のみの貨幣経済が一元的に行われたわけではない。かたや日本では15世紀に精錬技術が飛躍的に向上して銅生産が拡大し、銅は日明貿易(勘合貿易)や倭寇によって中国やヴェトナムに流入する。同じころ、永楽通宝といわれる銅貨が登場するが、日本との貿易にもっぱら使われ、明ではあまり流通せず、しかも私鋳が行われてきた。銅貨を取り巻く状況は非常に複雑で渾沌としていたのである。やがて明末に銀が登場するが、銀はあくまで秤量貨幣であって計数貨幣ではない。一般民衆が手にできるものではなく、末端では銅貨が用いられてきた。
撰銭だとか、貫高制から石高制への転換が室町・戦国時代を通じて日本では行われるが、かつて日本史の授業でならったこれらがいまひとつ腑に落ちないのは、「あとがき」の冒頭で筆者が書いている通りである。多くの人がいまだに完全に理解できていないのではないだろうか?筆者は長年の研究で端的な言葉で説明しているが、この本を読んでも筆者の理解に到達することは難しい。
というように、内容はなかなか難しいのだが、とても興味を引く問題が目白押しだった。特に第6章「貨幣システムと渡来銭」は貨幣制度そのものの理解に新しい視角を与えてくれる。
・石塚 真一著「BLUE GIANT MOMENTUM(5)」(小学館 ビッグコミックススペシャル)
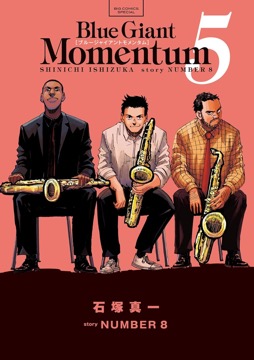
主人公のダイは、バンドメンバーのいるニューヨークを離れ、インターナショナル・ジャズ・コンペティションの行われるミズーリ州セントルイスに単身やってくる。そこで名うての若手サックスプレイヤーと競うべく、定められた10分の演奏を行う。予選を勝ち抜けるのは3人だけ…漫画のストーリーを細かく書くことはしたくないので短いがここまで。
・惣領 冬実著「カンツォニエーレ チェーザレ番外編」(コミックdays 講談社)
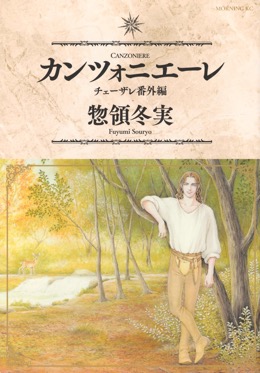
「チェーザレ 破壊の創造者」が13巻でストップしているが、これは本編からのスピンオフ作品。とはいえ、続編のようにも見える。「チェーザレ」第13巻で教皇選挙が行われた後、チェーザレの実父、ロドリーゴが教皇に就任し、チェーザレも枢機卿に任じられる。その時のチェーザレの秘めた恋についてが主題となっている。カンツォニエーレとは、ペトラルカの「抒情詩集」のイタリア語名。
相変わらず絵はきれいだし、惣領冬実が身を削って描いているのが想像できる。
この「チェーザレ」、本編はどうにも終わりそうにないが、スピンオフ作品でその空白を埋めていくのだろうか…
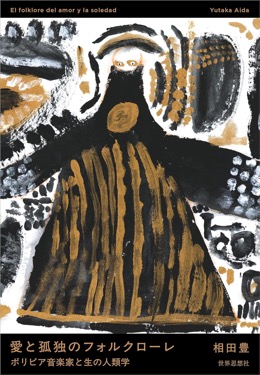
著者の相田さんは、実は私が一時だけ教えたことがあり、その後一時は同僚でもあった。彼は大学で中南米を対象とした人類学を専攻し、同好会でフォルクローレに魅せられ、フォルクローレ研究を進めてサンポーニャの演奏者にもなっているというユニークな研究者であり、現在は上智大学特任助教である。そのような学者がフィールドワークとしてボリビアの音楽家と交流し、文化人類学の論文とは異なるアプローチでこの大部な本を上梓した。博士論文を大幅にリライトしたものだそうだが、硬い論文の文体とは違い、一般読者にも実に読み易く、スルスルと内容がしみ渡ってくる。著者の逡巡も感じながら読んでいける。
・中村 隆之著「ブラック・カルチャー 大西洋を旅する声と音」(岩波新書)
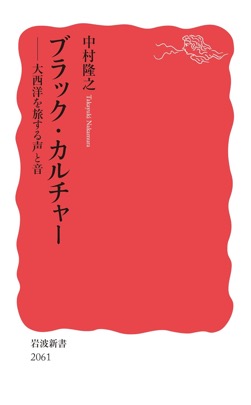
筆者はアメリカ合衆国のブラック・カルチャー専門家というよりは、カリブ海文学の専門家である。大変珍しい専門領域をお持ちのようだが、的確にアメリカ大陸全般のブラック・カルチャーの形成や展開を新書の中でまとめている。特にアメリカ大陸でのアフリカ系民族の奴隷制度との関連で、音楽だけでなく文学なども含めて理解する上では基礎的な内容になっているのだろう。ゴスペル、ジャズ、ソウル、ファンク、ヒップホップなどなど、ブラック・ミュージックを我々はジャンル分けしようとするが、それにはあまり意味はなく、根っこでいずれもが繋がっている。パン・アフリカニズムについて理解が深まったのが収穫だった。
・白井 聡・高瀬 毅(聞き手)「ニッポンの正体2025 世界の二極化と戦争の時代」(河出書房新社)
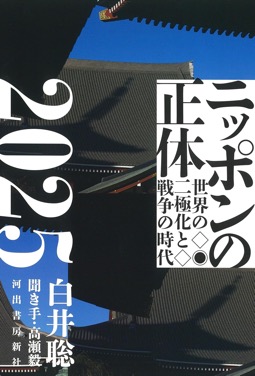
思想史家・政治学者で京都精華大学准教授の白井聡と、ジャーナリスト・ノンフィクション作家の高瀬毅との対談シリーズの最新作。白井の発言はときどき過激なものがあってドキッとする。
話題は国内政治状況(参院選を挟んで読んでいたので大変リアリティがあった)、東京一極集中、「戦後レジーム」について、大学の来し方行く末、労働について、「公助」の崩壊、朝鮮半島有事についてなど、多岐にわたっているが、最後の朝鮮半島有事については韓国の政権交代以前、トランプ再選以前の対談であり、現実が本の中の予測を追い越してしまっているので、賞味期限切れに近い。
全体として非常にわかりやすく、集中すれば数日間で読める。
・吉田 修一著「国宝 上」(朝日新聞出版)
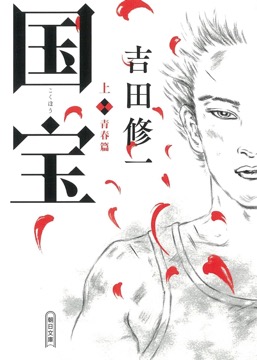
まず映画を鑑賞して、原作を読みたくなり、買い求めた。小説を読むのは実に久しぶりである。映画では描けなかった部分が描かれていて、一気にのめり込んだ。映画では描ききれなかった部分は複数あるのだが、ここで書いてしまっては元も子もないので書かないでおく。映画を観た後に読んでも、原作を先に読んで映画を観に行ってもどちらも楽しめるだろう。文体が「でございます。」というのも非常に珍しく、ユニークであった。上下巻だが、今月中に下巻まで読み切ることは難しかった。
上巻の後半は、主人公喜久雄の役者人生の中での天国と地獄が描かれる。映画では見られなかった、周辺人物や企業からのねちっこいいじめがすさまじい。
・黒田 明伸著「歴史の中の貨幣 銅銭がつないだ東アジア」(岩波新書)
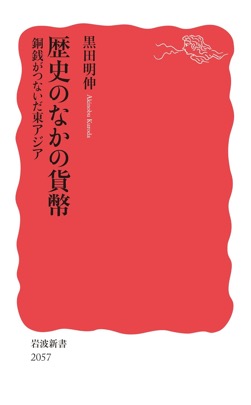
「国宝 上」と平行して月末から読み始めた。これがまたとても面白い内容だった。東アジアの銅銭として最も古いのは秦の半両銭、前漢の五銖銭であり、日本でも和同開珎以後「皇朝十二銭」が発行されてきた、というのが大学受験を前提とした貨幣史の基礎である。
だが、中国でも日本でも、貨幣経済がそのまま右肩上がりに進むのではなく、銅銭の製造に必要な銅鉱石の資源供給や精錬技術のハードルがあり、銅銭の品位の問題や流通範囲の限定などの結果、基本的には高額なもの(土地など)の対価としては絹や麻の布が用いられてきた。日本では、皇朝十二銭以後、戦国時代末期に至るまで自国で鋳造された貨幣は存在せず、中国から流入した銅銭が用いられ、銅銭は鋳つぶされて仏像や梵鐘などに再利用された。
租庸調をはじめ、銭納原則だった両税法でも現実には物納が行われてきた。それが宋代になって精練法の向上によって銅銭が大量発行され、交子や会子という手形から生まれた紙幣すら流通するようになった。このころ、大量に銅銭は日本にもたらされる。
元代になると、紙幣が主要通貨となり、原則中国では銅貨が使用できなくなる。これも大変ユニークなところ。明代初期も同様だが、紙幣のみの貨幣経済が一元的に行われたわけではない。かたや日本では15世紀に精錬技術が飛躍的に向上して銅生産が拡大し、銅は日明貿易(勘合貿易)や倭寇によって中国やヴェトナムに流入する。同じころ、永楽通宝といわれる銅貨が登場するが、日本との貿易にもっぱら使われ、明ではあまり流通せず、しかも私鋳が行われてきた。銅貨を取り巻く状況は非常に複雑で渾沌としていたのである。やがて明末に銀が登場するが、銀はあくまで秤量貨幣であって計数貨幣ではない。一般民衆が手にできるものではなく、末端では銅貨が用いられてきた。
撰銭だとか、貫高制から石高制への転換が室町・戦国時代を通じて日本では行われるが、かつて日本史の授業でならったこれらがいまひとつ腑に落ちないのは、「あとがき」の冒頭で筆者が書いている通りである。多くの人がいまだに完全に理解できていないのではないだろうか?筆者は長年の研究で端的な言葉で説明しているが、この本を読んでも筆者の理解に到達することは難しい。
というように、内容はなかなか難しいのだが、とても興味を引く問題が目白押しだった。特に第6章「貨幣システムと渡来銭」は貨幣制度そのものの理解に新しい視角を与えてくれる。
・石塚 真一著「BLUE GIANT MOMENTUM(5)」(小学館 ビッグコミックススペシャル)
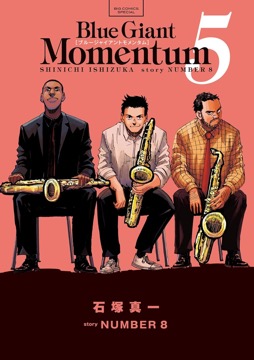
主人公のダイは、バンドメンバーのいるニューヨークを離れ、インターナショナル・ジャズ・コンペティションの行われるミズーリ州セントルイスに単身やってくる。そこで名うての若手サックスプレイヤーと競うべく、定められた10分の演奏を行う。予選を勝ち抜けるのは3人だけ…漫画のストーリーを細かく書くことはしたくないので短いがここまで。
・惣領 冬実著「カンツォニエーレ チェーザレ番外編」(コミックdays 講談社)
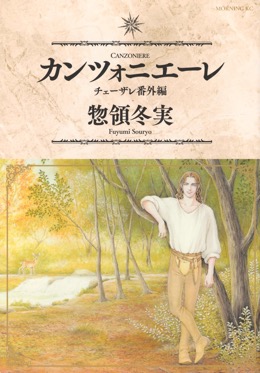
「チェーザレ 破壊の創造者」が13巻でストップしているが、これは本編からのスピンオフ作品。とはいえ、続編のようにも見える。「チェーザレ」第13巻で教皇選挙が行われた後、チェーザレの実父、ロドリーゴが教皇に就任し、チェーザレも枢機卿に任じられる。その時のチェーザレの秘めた恋についてが主題となっている。カンツォニエーレとは、ペトラルカの「抒情詩集」のイタリア語名。
相変わらず絵はきれいだし、惣領冬実が身を削って描いているのが想像できる。
この「チェーザレ」、本編はどうにも終わりそうにないが、スピンオフ作品でその空白を埋めていくのだろうか…
