September 2025
2025年9月に読んだ本
2025/09/08 Mon Filed in: 読んだ本
・安田 浩一著「地震と虐殺 1923ー2024」(中央公論新社)
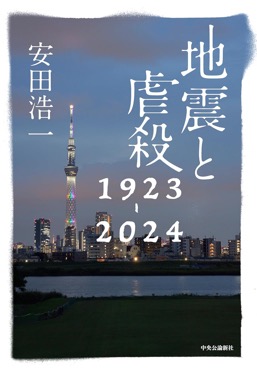
昨年秋に購入して、「積ん読」状態のまま1年が経ちそうだった。8月後半から読み始め、9月上旬に読了した。関東大震災から100年の年に読むよりも、関東大震災の起こったのと同じ時期に読みたかった。紙の書籍だと600ページもある大著である。
関東大震災直後、東京をはじめ、千葉、神奈川、群馬などで朝鮮人労働者や中国人労働者がかなりの数殺害された。これは否定することはできない事実である。この事実から目を背けたり、まして虐殺事件はなかったなどという世迷言を主張する者が現れ始め、各地の自称「保守」(実は保守の本質から大きく外れている)政治家たちがそれに便乗している。東京都知事小池百合子しかり、群馬県議会しかり。歴史を直視できない政治家は退場願いたい。
著者は各地の虐殺事件を追って現場を何度も訪れている。私の自宅がある近辺では震災直後にいくつもの虐殺事件が起こっているが、それらを文字で追うだけで痛ましい。昨年公開された映画、「福田村事件」も千葉県野田市での虐殺事件、しかも朝鮮出身者と見間違えられた香川県からの行商人が複数人、自警団の者たちに虐殺された。このような民衆たちによる虐殺事件は民衆の視野の狭さ、根拠のない噂に便乗してしまう弱さを著しているが、その背後で虐殺をけしかけ、自らも虐殺を率先して行った警察・軍隊の影響が強い。
著者のおかげで、虐殺を描いた絵画から、福島県西郷村でも虐殺事件が起こっていたことを知った。
・横山 百合子著「江戸東京の明治維新」(岩波新書)
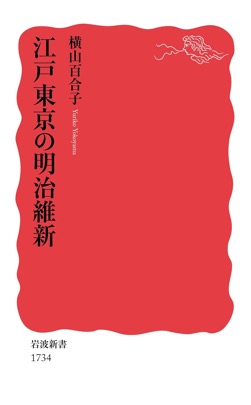
江戸末期から明治維新直後までの江戸の社会史を扱った本。大名屋敷の衰退と旧幕臣の生活、町人の暮らしっぷりや遊廓の変化、屠殺場の民衆など、一風変わったスポットを取り上げて論述している。
本書の「おわりに」に記された一節がこの本の特徴をよくあらわしているので、それを引用してみる。
「江戸東京の人びとにとって、明治維新とは何だったのか。混沌とする時代のなかで、旧来の身分の論理に拠って粘り強くたたかった者もあれば、集団から独立し、近代の一自営業者として新規事業に果敢に挑戦していく者もいた。役にたいする特権集団から、権利としての営業の自由と団結に気づきはじめる商人たちの姿もあった。維新を生きるとは、そうしたそれぞれの可能性を模索することであった。」
特に新吉原の遊女、「かしく」が社会的弱者であるにも関わらず精いっぱい自分の解放を求めて動く様は、感動的でもある。
・大山 顕著「マンションポエム東京論」(本の雑誌社)
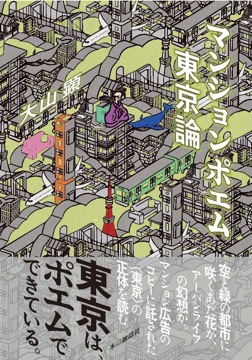
筆者はかつてテレビ番組「熱中時間 忙中"趣味"あり」にレギュラーとして出演していたコラムニストで、団地・工場・ジャンクションマニアとして知られていた人物である。この番組はけっこう好きで観ていたが、団地好きが高じてマンション広告の「ポエム」について掘り下げ、この本を上梓するに至ったことは、さして驚くできごとではなかった。
なかなか充実した書物である。今回は電子書籍が見つからなかったので、紙の本をネットで注文してお茶の水の丸善まで取りに行った。2段組、約350ページ。ある種学術的な本ではあるが、対象がマンションなので内容は分かりやすい。
「マンションポエム」とは、マンションの広告に掲載されているキャッチコピーである。たとえば、先の東京オリンピックの選手村を活用した「晴海フラッグ」は「美しい景色を眺めるたびに、町への愛着は深まっていくはずです。」銀座に近い高級マンションは「羨望の都心立地。」ここ数年で開発されタワーマンションが林窒する有明地区のマンションは「世界の羨望を集める 新たな中心を日本に。」といった具合である。
口の中に食べ物が入っていると外に飛び出しそうな噴飯物のコピーだが、筆者はもう25年もこういったコピーを集め、研究対象にしてきた。ポエムの対象は東京だけでなく、首都圏から関西(大坂・京都)地方都市にまで及ぶ。それらを読んでいるだけで面白いが、決してふざけた本ではない。マンションの構造や利便性は、東京だろうが地方都市だろうが、同年代に建設されたものであればさほど変わらない。問題は立地である。都心部からどのくらいの距離にあるのか、駅から徒歩何分なのか、公園や学校は近いのか、といった情報がその立地の価値を過剰に高め(あるいは高めることが困難で)マンションポエムに結びつくのだ。そういう点で、生々しい負の情報をマンションポエムは秘匿する役割を持つという。けだし名言だと思う。
・武田 砂鉄著「いきりの構造」(朝日新聞出)
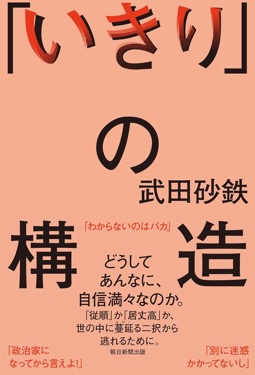
武田砂鉄の最新刊。彼の著作はかなり読んできた。「紋切型社会」以降、取り上げる問題や、ねちっこくて時に主旨が汲み取りにくい文体がほとんど変わっていないのがいい。
「いきり」とは何なのか?
暴走したりルールやマナーを守らない走行を繰り返す車両を見て、「イキった運転だなあ」と感想を漏らすことが自分にはある。例えば通勤中に見かけるのは、車線を踏んだまま右に行くのか左に車線変更するのかわかりにくい運転、事前にウィンカーを出さず、交差点の直前で急に点滅させ、右にいったん寄せてから左折する軽自動車、もちろん、「煽り運転」に限りになく近い、車間距離をとらない運転・・実は運転が「下手」だということをこれらの行為で表面化してしまっている。
日常生活上で「イキる」人を眼前で見かけたことはあまりないが、一言で言えば「自己中」な人、その強がった発言。他人からの異論に対して、自分の「正義」がまったく揺るがない態度を見せる人(相手の反論を「切り取り」と吐き捨てるような行為)、反吐が出るような自己防衛。武田砂鉄も、「おわりに」で「『いきり』は防衛なのだ」と述べている。
「いきり」は見苦しい。
・トマトスープ著「天幕のジャードゥーガル」(秋田書店 ボニータ・コミックス)
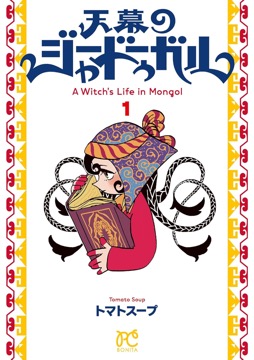
新しい漫画シリーズを手に入れて(実は大人買いして)読み始めた。まだ第1巻のみにとどめている。
13世紀初頭のモンゴル帝国の勢力拡大によって制圧されつつあった、イラン北東部(現在ならトゥルクメニスタン国境近く)の都市トゥースに住まう学者家族の少女奴隷、ステラ(のちにファーティマ)に起こる数奇な運命を描いている。
イランはイスラーム圏にあり、イスラーム圏での奴隷の扱い(19世紀のアメリカのそれとは大きく異なる)や学術を重んじる文化がよく描かれている。対するモンゴルは、自らを文化的には劣っていて、高度な学問を受け入れる意欲を持った社会と認めている。モンゴルによる中央アジア征服の中で、降伏と恭順の勧告を受け入れず、あくまでもモンゴルに抵抗する意志を持った都市では殺戮が行われたことが描かれている(これは事実である)。
フィクションではあるが、史実を踏まえて創られた物語であることは評価できそうだ。最近はそういった学術的な支えの中で描かれる漫画が増えて嬉しい。ただし、漫画の絵柄は、好みが分かれるところかもしれない。
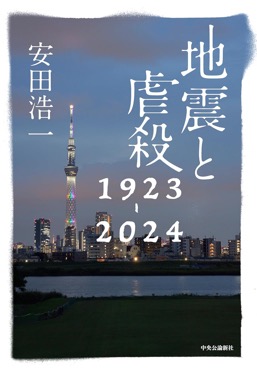
昨年秋に購入して、「積ん読」状態のまま1年が経ちそうだった。8月後半から読み始め、9月上旬に読了した。関東大震災から100年の年に読むよりも、関東大震災の起こったのと同じ時期に読みたかった。紙の書籍だと600ページもある大著である。
関東大震災直後、東京をはじめ、千葉、神奈川、群馬などで朝鮮人労働者や中国人労働者がかなりの数殺害された。これは否定することはできない事実である。この事実から目を背けたり、まして虐殺事件はなかったなどという世迷言を主張する者が現れ始め、各地の自称「保守」(実は保守の本質から大きく外れている)政治家たちがそれに便乗している。東京都知事小池百合子しかり、群馬県議会しかり。歴史を直視できない政治家は退場願いたい。
著者は各地の虐殺事件を追って現場を何度も訪れている。私の自宅がある近辺では震災直後にいくつもの虐殺事件が起こっているが、それらを文字で追うだけで痛ましい。昨年公開された映画、「福田村事件」も千葉県野田市での虐殺事件、しかも朝鮮出身者と見間違えられた香川県からの行商人が複数人、自警団の者たちに虐殺された。このような民衆たちによる虐殺事件は民衆の視野の狭さ、根拠のない噂に便乗してしまう弱さを著しているが、その背後で虐殺をけしかけ、自らも虐殺を率先して行った警察・軍隊の影響が強い。
著者のおかげで、虐殺を描いた絵画から、福島県西郷村でも虐殺事件が起こっていたことを知った。
・横山 百合子著「江戸東京の明治維新」(岩波新書)
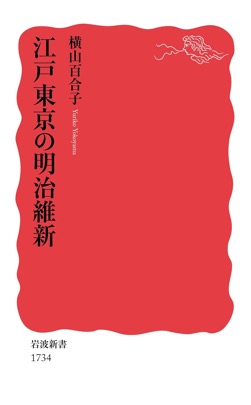
江戸末期から明治維新直後までの江戸の社会史を扱った本。大名屋敷の衰退と旧幕臣の生活、町人の暮らしっぷりや遊廓の変化、屠殺場の民衆など、一風変わったスポットを取り上げて論述している。
本書の「おわりに」に記された一節がこの本の特徴をよくあらわしているので、それを引用してみる。
「江戸東京の人びとにとって、明治維新とは何だったのか。混沌とする時代のなかで、旧来の身分の論理に拠って粘り強くたたかった者もあれば、集団から独立し、近代の一自営業者として新規事業に果敢に挑戦していく者もいた。役にたいする特権集団から、権利としての営業の自由と団結に気づきはじめる商人たちの姿もあった。維新を生きるとは、そうしたそれぞれの可能性を模索することであった。」
特に新吉原の遊女、「かしく」が社会的弱者であるにも関わらず精いっぱい自分の解放を求めて動く様は、感動的でもある。
・大山 顕著「マンションポエム東京論」(本の雑誌社)
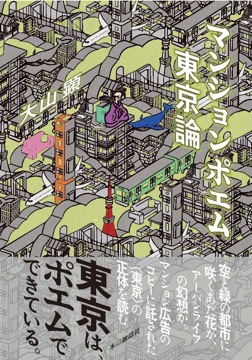
筆者はかつてテレビ番組「熱中時間 忙中"趣味"あり」にレギュラーとして出演していたコラムニストで、団地・工場・ジャンクションマニアとして知られていた人物である。この番組はけっこう好きで観ていたが、団地好きが高じてマンション広告の「ポエム」について掘り下げ、この本を上梓するに至ったことは、さして驚くできごとではなかった。
なかなか充実した書物である。今回は電子書籍が見つからなかったので、紙の本をネットで注文してお茶の水の丸善まで取りに行った。2段組、約350ページ。ある種学術的な本ではあるが、対象がマンションなので内容は分かりやすい。
「マンションポエム」とは、マンションの広告に掲載されているキャッチコピーである。たとえば、先の東京オリンピックの選手村を活用した「晴海フラッグ」は「美しい景色を眺めるたびに、町への愛着は深まっていくはずです。」銀座に近い高級マンションは「羨望の都心立地。」ここ数年で開発されタワーマンションが林窒する有明地区のマンションは「世界の羨望を集める 新たな中心を日本に。」といった具合である。
口の中に食べ物が入っていると外に飛び出しそうな噴飯物のコピーだが、筆者はもう25年もこういったコピーを集め、研究対象にしてきた。ポエムの対象は東京だけでなく、首都圏から関西(大坂・京都)地方都市にまで及ぶ。それらを読んでいるだけで面白いが、決してふざけた本ではない。マンションの構造や利便性は、東京だろうが地方都市だろうが、同年代に建設されたものであればさほど変わらない。問題は立地である。都心部からどのくらいの距離にあるのか、駅から徒歩何分なのか、公園や学校は近いのか、といった情報がその立地の価値を過剰に高め(あるいは高めることが困難で)マンションポエムに結びつくのだ。そういう点で、生々しい負の情報をマンションポエムは秘匿する役割を持つという。けだし名言だと思う。
・武田 砂鉄著「いきりの構造」(朝日新聞出)
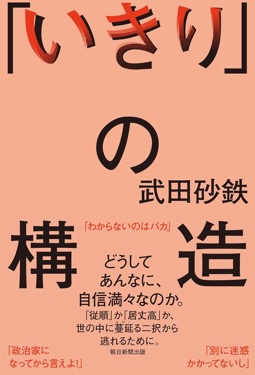
武田砂鉄の最新刊。彼の著作はかなり読んできた。「紋切型社会」以降、取り上げる問題や、ねちっこくて時に主旨が汲み取りにくい文体がほとんど変わっていないのがいい。
「いきり」とは何なのか?
暴走したりルールやマナーを守らない走行を繰り返す車両を見て、「イキった運転だなあ」と感想を漏らすことが自分にはある。例えば通勤中に見かけるのは、車線を踏んだまま右に行くのか左に車線変更するのかわかりにくい運転、事前にウィンカーを出さず、交差点の直前で急に点滅させ、右にいったん寄せてから左折する軽自動車、もちろん、「煽り運転」に限りになく近い、車間距離をとらない運転・・実は運転が「下手」だということをこれらの行為で表面化してしまっている。
日常生活上で「イキる」人を眼前で見かけたことはあまりないが、一言で言えば「自己中」な人、その強がった発言。他人からの異論に対して、自分の「正義」がまったく揺るがない態度を見せる人(相手の反論を「切り取り」と吐き捨てるような行為)、反吐が出るような自己防衛。武田砂鉄も、「おわりに」で「『いきり』は防衛なのだ」と述べている。
「いきり」は見苦しい。
・トマトスープ著「天幕のジャードゥーガル」(秋田書店 ボニータ・コミックス)
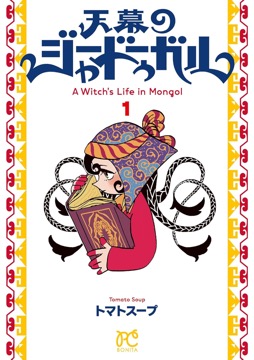
新しい漫画シリーズを手に入れて(実は大人買いして)読み始めた。まだ第1巻のみにとどめている。
13世紀初頭のモンゴル帝国の勢力拡大によって制圧されつつあった、イラン北東部(現在ならトゥルクメニスタン国境近く)の都市トゥースに住まう学者家族の少女奴隷、ステラ(のちにファーティマ)に起こる数奇な運命を描いている。
イランはイスラーム圏にあり、イスラーム圏での奴隷の扱い(19世紀のアメリカのそれとは大きく異なる)や学術を重んじる文化がよく描かれている。対するモンゴルは、自らを文化的には劣っていて、高度な学問を受け入れる意欲を持った社会と認めている。モンゴルによる中央アジア征服の中で、降伏と恭順の勧告を受け入れず、あくまでもモンゴルに抵抗する意志を持った都市では殺戮が行われたことが描かれている(これは事実である)。
フィクションではあるが、史実を踏まえて創られた物語であることは評価できそうだ。最近はそういった学術的な支えの中で描かれる漫画が増えて嬉しい。ただし、漫画の絵柄は、好みが分かれるところかもしれない。
