October 2025
2025年10月に読んだ本
2025/10/30 Thu Filed in: 読んだ本
・トマトスープ著「天幕のジャードゥーガル 1〜5」(秋田書店ボニータコミックス)
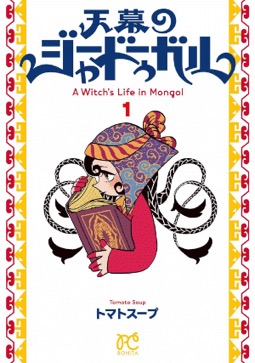
いままで読みたいと思っていて買うことを躊躇していた漫画。舞台は13世紀のモンゴル帝国。主人公はイラン東部の町トゥースの女奴隷、シタラ。学者一家の聡明な奴隷だったシタラはモンゴル帝国の膨張に巻き込まれ、流れ流れてモンゴル帝国のオゴデイの妃、ドレゲネの侍女となる。シタラ(もとの女主人の名ファーティマと改名)はモンゴル帝国への復讐心からその地位を利用して妃を通じて政治工作を繰り広げる。モンゴル帝国の後宮の女性たちも、それぞれの思惑からモンゴル帝国のリーダー(大ハーンや将軍たち)への謀略を進めていき、そこで自由に動けるシタラを利用しようとする。
ざっと言えばそんな話である。モンゴル帝国と言えばチンギス・ハーンかフビライにしか関心は向かないが、オゴデイやチャガタイ、グユク、トゥルイなどに注目しているのはユニークである。トマトスープは漫画家としてのペンネームだが、女性らしい。手塚治虫に少し似た筆致で歴史漫画を描いている。人物の見分けが難しい、近接したキャラクターがちょっと難点。
当時の女性だけでそこまで深い陰謀が描けたのかどうかは疑問だが、これからの展開がどうなるのか、興味は湧く。
この漫画もアニメ化が予定されているらしい。
・幸村 誠著「ヴィンランド・サガ 29」(講談社アフタヌーンコミックス)
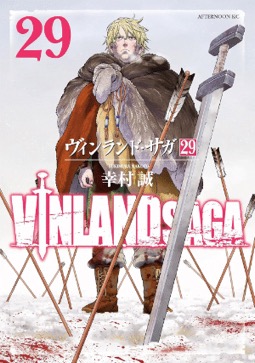
ついに29巻で完結。11世紀に実在した商人トルフィン・ソルザルソンをモデルとする物語も、ヴィンランドでの植民活動のさなか、先住民との対立や先住民に流行しはじめた疫病をめぐって窮地に立たされる。
村のリーダー、トルフィンはあくまでも平和的に先住民との友好を重視し、植民村からの一時撤退も決意するのだが、すでにこの地で苦労を重ねながら生活を軌道に乗せてきた村民にとっては、撤退は考えられない。対立する先住民からの攻撃を受けると自己防衛のために先住民を殺戮し、平和的だった村民も攻撃的に傾斜していく。
少年時代に短剣一本で激しく戦ってきたトルフィンには、すでに力による決着を超越した決意が確固たるものとなっていた。彼だけがあくまでも村の存亡の危機に流されず、先住民との共存を実現しようとしている。今まで共に歩んできた親友ですらも、先住民に対する憎悪にまみれ、ついに命を落とす。
誰が本当の戦士なのか?
真の戦士とは、父の最期を見届けたトルフィンの中でのみ完成していた・・・
この漫画も、すでにアニメ化が何度かに分けて行われている。
・森山 伸也編「FREE HEEL BOOK -Telemark Ski- vol.2」(同人誌)
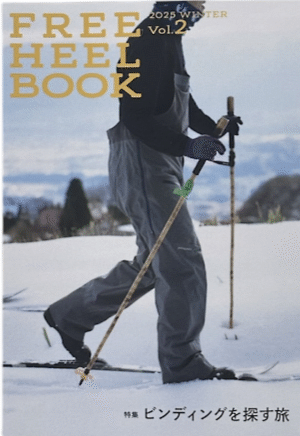
新しいスキー板に今までの古い板からビンディングを移植するための付け替え作業のため、目白のカラファテに立ち寄った際に見つけて衝動買いした本。価格は3,300円だが、こういう本を購入するのに価格の高さを云々言ってはいけない。私自身、テレマークビンディングを探す長い旅の途中である。
テレマークスキーをいまコンスタントに滑っている人口はどのくらいなのだろうか?
私がテレマークスキーを始めた1990年代前半の頃に比べると、特定のスキー場や雪山に集中するのではなく、全国に分散したような気がする。一方、当時初心者として技術の向上に明け暮れていたために、かつての方がずっと熱気があったような気もしている。
この本を読むと、ビンディングにこだわる人たちの細かなセッティングや部品選びが詳細に書かれていて熱気が伝わってくる。アルペンスキーのビンディングとは異なり、テレマークスキーのビンディングはスキーヤーの骨格や体格、滑りのクセ、どんなブーツを履いているか、になどによって千差万別であっておかしくない。それだけ、テレマークのあり方は正解が広い。そのために、軽量・シンプル、自分に合ったビンディングをフランケンシュタインのように別々の製品の組み合わせから作ってしまう人もいるのだ。もちろん、規格が明確に定まっているわけではないから、部品の寄せ集めだけでは使い物にならず、手製のパーツを組み合わせて納得のいくものに仕上げている。その努力は見上げたものだ。私にはそこまで拘れるだけの動機がない。
この本の入手先はこちらから
・藤田 直哉著「攻殻機動隊論 新版2025」(作品社)
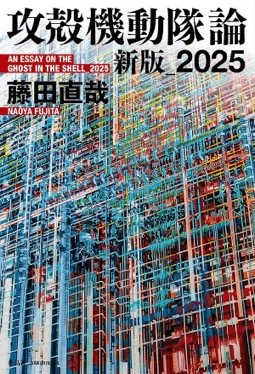
10月半ばからは3冊の本を平行して呼んでいたので、どの本もなかなか読了までに至らなかった。この『攻殻機動隊論』と、野家啓一『パラダイムとは何か クーンの科学史革命』、松原圭一郎『海を越えて 人の移動をめぐる物語』である。『攻殻機動隊論』だけは月末にようやく読み終えた。しかし、この本(紙で買っている)の総ページは380ページ。ポイントも小さくてなかなか読了するのには骨が折れた。
「攻殻機動隊」は1989年に連載が始まった士郎正宗の漫画を発端として、95年の押井守監督『攻殻機動隊 ghost in the shell」を起点とするアニメ映画、TVシリーズなどを指す。最近ではNetflixで配信された『攻殻機動隊 2045』の2つのシリーズがある。また26年には新しい「攻殻機動隊」のアニメ版が予定されている。
これらの映像作品についてそれぞれ論じているのがこの本である。時に南海でわかりにくく、よくある評論本の形式だが、映像は何度も見ているのでそれなりに楽しめた。
今月は3冊を平行して呼んでいたこともあるが、なかなか読書時間を確保できなかった・・
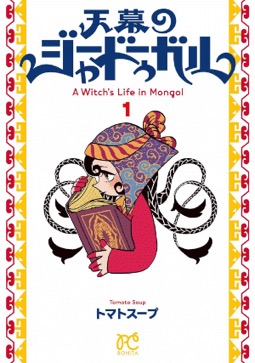
いままで読みたいと思っていて買うことを躊躇していた漫画。舞台は13世紀のモンゴル帝国。主人公はイラン東部の町トゥースの女奴隷、シタラ。学者一家の聡明な奴隷だったシタラはモンゴル帝国の膨張に巻き込まれ、流れ流れてモンゴル帝国のオゴデイの妃、ドレゲネの侍女となる。シタラ(もとの女主人の名ファーティマと改名)はモンゴル帝国への復讐心からその地位を利用して妃を通じて政治工作を繰り広げる。モンゴル帝国の後宮の女性たちも、それぞれの思惑からモンゴル帝国のリーダー(大ハーンや将軍たち)への謀略を進めていき、そこで自由に動けるシタラを利用しようとする。
ざっと言えばそんな話である。モンゴル帝国と言えばチンギス・ハーンかフビライにしか関心は向かないが、オゴデイやチャガタイ、グユク、トゥルイなどに注目しているのはユニークである。トマトスープは漫画家としてのペンネームだが、女性らしい。手塚治虫に少し似た筆致で歴史漫画を描いている。人物の見分けが難しい、近接したキャラクターがちょっと難点。
当時の女性だけでそこまで深い陰謀が描けたのかどうかは疑問だが、これからの展開がどうなるのか、興味は湧く。
この漫画もアニメ化が予定されているらしい。
・幸村 誠著「ヴィンランド・サガ 29」(講談社アフタヌーンコミックス)
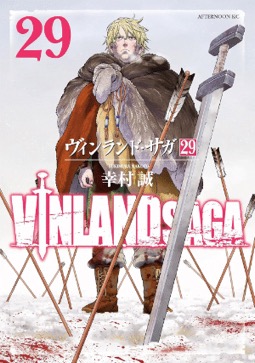
ついに29巻で完結。11世紀に実在した商人トルフィン・ソルザルソンをモデルとする物語も、ヴィンランドでの植民活動のさなか、先住民との対立や先住民に流行しはじめた疫病をめぐって窮地に立たされる。
村のリーダー、トルフィンはあくまでも平和的に先住民との友好を重視し、植民村からの一時撤退も決意するのだが、すでにこの地で苦労を重ねながら生活を軌道に乗せてきた村民にとっては、撤退は考えられない。対立する先住民からの攻撃を受けると自己防衛のために先住民を殺戮し、平和的だった村民も攻撃的に傾斜していく。
少年時代に短剣一本で激しく戦ってきたトルフィンには、すでに力による決着を超越した決意が確固たるものとなっていた。彼だけがあくまでも村の存亡の危機に流されず、先住民との共存を実現しようとしている。今まで共に歩んできた親友ですらも、先住民に対する憎悪にまみれ、ついに命を落とす。
誰が本当の戦士なのか?
真の戦士とは、父の最期を見届けたトルフィンの中でのみ完成していた・・・
この漫画も、すでにアニメ化が何度かに分けて行われている。
・森山 伸也編「FREE HEEL BOOK -Telemark Ski- vol.2」(同人誌)
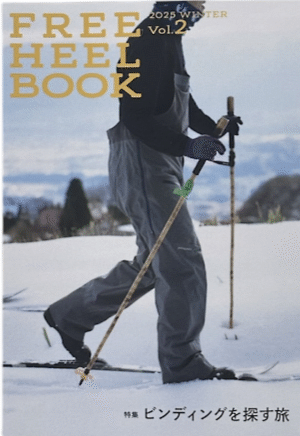
新しいスキー板に今までの古い板からビンディングを移植するための付け替え作業のため、目白のカラファテに立ち寄った際に見つけて衝動買いした本。価格は3,300円だが、こういう本を購入するのに価格の高さを云々言ってはいけない。私自身、テレマークビンディングを探す長い旅の途中である。
テレマークスキーをいまコンスタントに滑っている人口はどのくらいなのだろうか?
私がテレマークスキーを始めた1990年代前半の頃に比べると、特定のスキー場や雪山に集中するのではなく、全国に分散したような気がする。一方、当時初心者として技術の向上に明け暮れていたために、かつての方がずっと熱気があったような気もしている。
この本を読むと、ビンディングにこだわる人たちの細かなセッティングや部品選びが詳細に書かれていて熱気が伝わってくる。アルペンスキーのビンディングとは異なり、テレマークスキーのビンディングはスキーヤーの骨格や体格、滑りのクセ、どんなブーツを履いているか、になどによって千差万別であっておかしくない。それだけ、テレマークのあり方は正解が広い。そのために、軽量・シンプル、自分に合ったビンディングをフランケンシュタインのように別々の製品の組み合わせから作ってしまう人もいるのだ。もちろん、規格が明確に定まっているわけではないから、部品の寄せ集めだけでは使い物にならず、手製のパーツを組み合わせて納得のいくものに仕上げている。その努力は見上げたものだ。私にはそこまで拘れるだけの動機がない。
この本の入手先はこちらから
・藤田 直哉著「攻殻機動隊論 新版2025」(作品社)
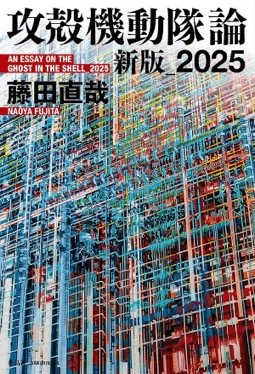
10月半ばからは3冊の本を平行して呼んでいたので、どの本もなかなか読了までに至らなかった。この『攻殻機動隊論』と、野家啓一『パラダイムとは何か クーンの科学史革命』、松原圭一郎『海を越えて 人の移動をめぐる物語』である。『攻殻機動隊論』だけは月末にようやく読み終えた。しかし、この本(紙で買っている)の総ページは380ページ。ポイントも小さくてなかなか読了するのには骨が折れた。
「攻殻機動隊」は1989年に連載が始まった士郎正宗の漫画を発端として、95年の押井守監督『攻殻機動隊 ghost in the shell」を起点とするアニメ映画、TVシリーズなどを指す。最近ではNetflixで配信された『攻殻機動隊 2045』の2つのシリーズがある。また26年には新しい「攻殻機動隊」のアニメ版が予定されている。
これらの映像作品についてそれぞれ論じているのがこの本である。時に南海でわかりにくく、よくある評論本の形式だが、映像は何度も見ているのでそれなりに楽しめた。
今月は3冊を平行して呼んでいたこともあるが、なかなか読書時間を確保できなかった・・
